|
第3章 なんでも徹底比較「地球と惑星」(2)
11.水星の1日は2年ってどういうこと?
12.ビーナスのベールの影には灼熱地獄が・・・金星の正体
13.太陽になりそこねた星、木星
14.木星の衛星「エウロパ」には生命体が存在する?!
15.水に浮く惑星、土星の秘密
16.天王星は一番のひょうきん者
17.冥王星は惑星なのか?
18.太陽系の放浪者、彗星
19.太陽系のオデッセイ、ボイジャーの旅はいつまでつづく?
<コラム>
世紀末の星空は、夢で明るい
11.水星の1日は2年ってどういうこと?
水星は太陽にいちばん近いために、公転周期が非常に短い。また、公転軌道はかなりいびつだ。これがあるために、水星上ではいろいろ面白いことが起こる。
まず、水星の1日は1年よりも長い。これは、水星の自転周期が非常に長く、公転周期が非常に短いことからくる。1.5回自転する間に1回公転することが知られている。
これから、水星では1日半で1年がたってしまうと結論するのは早すぎる。私たちがいう1日とは、その星が1回転することではなく、その星が太陽に対して1回転することをいっているからだ。
星それ自身の回転(自転)数で数える日にちのことを恒星日といい、星の太陽に対する回転数で数える日にちのことを太陽日という。惑星は太陽の周りを公転しているので、太陽日はその公転の影響を受ける。したがって、太陽日と恒星日とは一致しない。
もちろん地球も例外ではなく、太陽日の1日は24時間だが、恒星日の1日は23時間56分4秒(=自転周期)である。つまり、恒星日の1日がたっても(地球が1回転しても)太陽日の1日は3分56秒を残してまだ終わらない。この差の時間を365倍すると、ちょうど23時間56分4秒となって、恒星日の1日と一致する。つまり、太陽日で365日(1年)がたったとき、恒星日では1日多い366日がたっている。これは、地球が1公転する(1年がたつ)間に366回自転しているということである。
地球の公転周期と自転周期との比は上述したごとく 366:1 である。そして366と1との差が太陽日で表された地球の公転周期となる。つまり365日だ。この365日の間に地球は366回自転し、1公転する。
水星の場合はどうであろう。水星の公転周期と自転周期は、24時間を1日として数えるとそれぞれ88日と59日である*1。水星の1恒星日が59日に相当するわけだ。このことから水星の公転周期を水星の恒星日で表すと 88÷59=1.5 だから1.5日となる。つまり、水星の公転周期と自転周期との比は 1.5:1 だ。したがって、1.5と1の差である0.5日が太陽日で表された水星の公転周期となる。つまり半日だ。この半日の間に1.5回転し、1公転する。何と、半日で1年がたってしまうのだ。1日だと2年である。
この比が 1:1 の惑星*2だとどうなるだろう。1-1=0 だから、太陽日で表されたこの惑星の公転周期はゼロである。つねに同じ面を太陽に向けて公転しているということだ。いつまでたっても昼は昼のままということである。裏側はもちろん常時夜だ。何回公転してもそれは変わらないから、日がたたないのに年数だけがたっていくという奇妙なことになる。
もっと面白いのは、公転周期のほうが自転周期よりも短い惑星の場合だ。恒星日で表された両者の比が仮に 0.5:1 であるとすると、太陽日のマイナス0.5日で惑星は半回転し、1公転する。これはどういうことかというと、太陽が西から昇って、東へ動くのである。つまり、日はさかさまにたっていき、それの半日で1年が経過するのだ。1日だと2年である。これは現実に起こっている。いびつな軌道を回る水星は、太陽にもっとも近づく近日点付近にいるときには公転速度がいっそう速まるから、一時的に自転周期よりも公転周期のほうが短くなる。したがってこの間だけ、水星では太陽が西から東へ動く。
*1 これらの日数は恒星日でも太陽日でもなく、便宜的に日数で表された“時間”である。
*2 惑星ではなく地球の衛星ではあるが「月」がこれに相当する。公転周期と自転周期が同じで同期しているために、月はつねに同じ面を地球に向けている(第1章の11参照)。
12.ビーナスのベールの影には灼熱地獄が・・・金星の正体
金星は「宵の明星」とも「明けの明星」とも呼ばれる。日没後に最初に西の空に見えるので宵の明星、また、明け方最後まで東の空に残っているので明けの明星となったわけだ。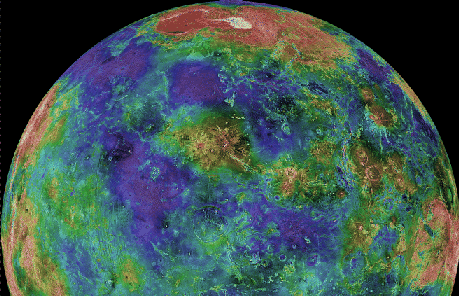
ヨーロッパでは、金星はビーナスと命名されているが、それは、古代人が知っているいちばん明るい星だったからであろう。なぜそんなに明るいかというと、距離的に地球から近いというだけでなく、金星を覆っている厚い雲のためである。おもに濃硫酸でできているこの雲は、太陽光の八〇%近くを反射するという。雲の下の大気はほとんどが二酸化炭素で、気圧は何と九〇気圧。地球の海面下一〇〇〇mの圧力とほぼ同じだ。
厚い雲と二酸化炭素の大気は、地球では想像もつかない温室効果をもたらし、金星の表面温度をおよそ一二七度~四六七度以上(鉛が溶ける温度)にまで上げている。水星より二倍も太陽から離れているにもかかわらず、水星より温度が高い。大気のほとんどない水星では、温室効果が現われないのだ。これでわかるように、ビーナスの厚い雲のベールの影には、すさまじい灼熱地獄が隠されている。
金星の軌道は、太陽系の惑星の中でもっとも円に近く、離心率はわずかに一%以下。また、自転周期が二四三日と太陽系惑星の中ではいちばん長く、公転周期(二二五日)のほうが短い。しかも、自転の向きが他の太陽系惑星とは逆向きだ。これだと、太陽が西から昇る要因が二つ重なるので、結局、太陽は東から昇ることになる。
地球の隣どうしの惑星である火星と金星は、ともに地球とよく似ている。が、その似姿は天と地ほどに異なる。一方は極寒の地であり、もう一方は灼熱地獄だ。
金星が地球と似ている点をあげてみよう。
①金星は地球よりもほんの少し小さいだけ(直径は地球の九五%、質量は八〇%)。
②どちらの惑星にもほとんどクレーターがなく、表面が比較的若い。
③化学組成が似通っている。
太古の金星には、海があったかもしれない。しかし、金星は地球よりも太陽に近いために温度が高いのと、大陸が存在しないのとで、最終的には温室効果が勝ちをおさめ、海は干上がってしまったらしい。
13.太陽になりそこねた星、木星
ひとくちに太陽系惑星といっても、実は、二つのグループに分かれて進化していった。一方は地球のような岩石を主体とした惑星、もう一方は木星のようなガスを主体とした惑星だ。前者は地球型惑星と呼ばれ、水星、金星、地球、火星が含まれる。後者は木星型惑星といい、木星、土星、天王星、海王星が含まれる。
冥王星は奇妙なことに地球型だ。しかも、この星の公転軌道の近日点は海王星の内側である。
このことから、冥王星は海王星の衛星だったとも、大きな小惑星ないしは彗星だともいわれる(本章の17参照)。
木星型惑星の進化過程はこうだ。
微惑星の合体によって惑星が形成されつつあるとき、太陽から遠いところにある木星型惑星では温度が非常に低かったために、微惑星に含まれる水やメタン、アンモニアなどは凍って固体となり、惑星を形づくる材料の一部となった。太陽から近い地球型惑星だと液化するか気化してしまうこれらの物質が、木星型惑星では惑星の原材料となったわけである。このために、木星型惑星はより大きくなって質量を増大させ、ついには微惑星のまにまに漂っていた水素やヘリウムなどの軽い気体までも吸引した。
周辺に大量の微惑星があったために、特に巨大化した木星はとりわけ大量の水素を集め、太陽系の中では最大、最重量の惑星となった。他の全惑星を合わせたよりも二倍も重く、その組成に水素が占める割合は九〇%にも及ぶ。
木星の核は、地球よりも一〇倍以上も重い岩石からなる。地球の核とマントルとが一つに押し込められた状態といっていいだろう。核の外側には、金属水素と液体水素の層がある。あまりの超高圧のために原子の構造が破壊され、電子が陽子の束縛から自由になって、金属と似たような状態になっているのが金属水素、そこまではいかないが、液状に押しつぶされているのが液体水素だ。最外殻を覆う大気層は大部分が水素で、そのほかにヘリウム、微量のメタン、水蒸気、二酸化炭素が含まれる。
水素の星、木星は、あと一〇〇倍の質量があれば、同じ水素の星である太陽になったであろうといわれている。
14.木星の衛星「エウロパ」には生命体が存在する?!
宇宙船ボイジャーが次々に送ってよこした惑星写真の数々。あまりの鮮明さに、度肝を抜かれた人も多かったであろう。その中の木星の写真を見ると、帯模様が目立つ。そして、ひときわ目立つのが楕円形の赤い模様だ。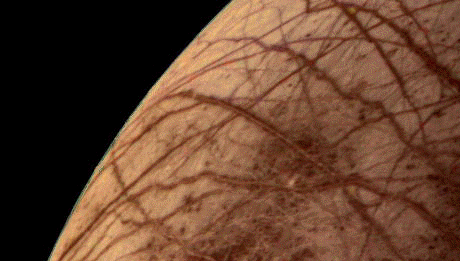
これは大赤斑と呼ばれ、三〇〇年も前に発見されている。長軸二万五〇〇〇km、短軸一万二〇〇〇kmという巨大な渦で、長さだけなら地球二個がまるまる入る大きさだ。台風のようなものとも考えられるが、台風が風を巻き込むのに対し、こちらは大気の下層から雲が涌き上がってできたものだ。地球の台風は一過性なのに、こちらは少なくとも三〇〇年前以前から存在し、これから先いつまで存続するのか、まったくわからない。
木星の大気の表面は、緯線方向に沿って高速で動いている。つまり風だ。しかも、この風は帯域をなし、隣り合う帯域どうし互いに反対方向に吹いている。これらの帯域の化学組成や温度のわずかな相違が、木星の帯模様の原因だ。
木星はまた、地球よりもはるかに強い巨大な磁場をもっている。金属水素の対流が原因であろう。この強力な磁場は、高エネルギーの放射能(宇宙線)を大量に捕捉するから、保護されていない人間が木星に近づけば即死する。もちろん、宇宙船そのものにも悪影響が及ぶ。木星を訪れる宇宙船と宇宙飛行士には放射能対策が必須だ。
さて、木星には一六個の衛星があることが知られている。その中でもサイズの大きい四つ、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストは、ガリレオが見つけたことからガリレオ衛星と呼ばれる。木星で面白いのは、木星そのものよりもこれらの衛星だ。古くはボイジャー、最近ではガリレオ探査機やハッブル宇宙望遠鏡によって詳しく観測され、いろいろなことがわかってきた。
まずイオであるが、この衛星には活火山がある。ボイジャーが初めて見つけた。もっとも巨大で活動的な火山は、高度三〇〇kmにも達する噴煙を上げる。これだけの高さの噴煙を形成するには、時速三〇〇〇km以上の噴出速度が必要だという。激しく活動するこの熱い星には氷はない。
お次はエウロパだが、この衛星には生命体が存在する可能性があるという。クレーターのない非常になめらかな表面は、岩と氷原で覆われている。ところどころが割れた氷原の下には、深さ五〇kmに及ぶ液体の層があるとみられる。この液体は火山活動によって温められ、生命体が存在しうる環境を形成している可能性がある。また非常に希薄な酸素を含む大気も存在する。
残る二つの衛星、ガニメデとカリストのうち、ガニメデは太陽系最大の衛星である。両衛星とも岩石の核をもつ氷の衛星だ。
15.水に浮く惑星、土星の秘密
土星は、太陽系惑星の中でもっとも密度の小さい星である。その比重は水より小さく〇・七。つまり、土星は水に浮くのだ。
土星の大きさは木星の八四%ぐらいで、木星に次ぐ大きさの惑星である。またその組成は水素が七五%近くを占め、木星の九〇%に対してもそんなに変わらない。ところが、その質量は木星の約三〇%しかない。密度が小さいのは当然であろう。これは、質量が小さいために土星内部の圧力が木星ほどには強くはならず、そのため、高密度の金属水素(本章の13参照)の層があまりできずに、ほとんどが密度の低い液体水素の層だけになっていることからきている。
土星といえば、あの神秘的なリングである。直径は二五万kmもある。地球の直径の二〇倍近い。ところが、その厚さは二〇〇mぐらいしかない。直径が厚さの一二五万倍もある円盤を思い浮かべるのは、なかなか困難だ。無数の氷の塊や氷結した岩石が、同心円状に回転しているのがリングに見えるのである。
土星の南北両極にはオーロラもできる。同様なオーロラは木星にもできるが、これらは紫外線領域でないとよく見えなかったり、撮影装置の解像度がイマイチだったりで、これまでは鮮明な映像は撮れなかった。その難関を、ハッブル宇宙望遠鏡に搭載された新開発の分光画像装置(STIS)がクリアし、これまで見たこともない土星の鮮明なオーロラ映像を宇宙から送ってよこした。これによって、球体の真ん中にはリング、両極にはオーロラという、土星の新しいイメージが浮かび上がった。
ところでNASAは、一九九七年一〇月に、初の土星探査機であるカッシーニを打ち上げた。電源にプルトニウムを用いているために、事故でまき散らされる恐れがあるとして、環境保護団体が以前から中止を求めていたものである。それでもあえて打ち上げられたカッシーニは、機体の高さが六・八m、重量は五・七トンにもなるNASAにとっては最後の“重厚長大”宇宙船で、二〇〇四年に土星に到着する。土星本体、衛星群、リング、磁気圏などの調査を行なう。ハイライトは、土星軌道上において、欧州宇宙機関(ESA)の観測機、ホイヘンスを土星の衛星タイタンにパラシュートで突入させるミッションだ。探査は四年にわたってつづけられるという。
16.天王星は一番のひょうきん者!
土星よりも遠い惑星を訪れた宇宙船はただ一機、ボイジャー二号だけだ。天王星と海王星を訪れている。両星とも青い色をし、組成もほぼ同じだ。大部分は岩石と氷で、水素の占める割合は一五%ほどである。また、液体水素の層がない。大気はほとんどが水素で、そのほかにヘリウムと微量のメタンが含まれる。大きさでいうと、天王星は土星に次いで大きく(全惑星中三番目)、海王星は天王星よりも若干小さい。しかし、質量は海王星のほうが大きい。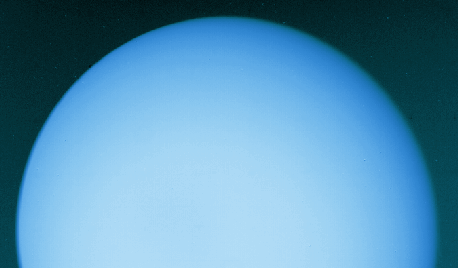
天王星最大の特徴は、自転軸が横倒しになっていることである。つまり公転面に寝そべっているような状態だ。自転軸の傾きというのは、自転軸が公転面に対して垂直になっていないことをいうが、天王星はその傾きの角度がほぼ九〇度(九七度九分)なので横倒し状態になっているわけだ。その倒れた向きをつねに不変に保ちながら*、太陽のまわりを公転しているのである。
地球のように、ほどよく自転軸が傾いている(二三・五度)と四季があるが、自転軸がほぼ九〇度傾いて公転面に横倒しになっている天王星ではどうなのだろう? 第1章の12で述べたことを思い出しつつ、天王星の自転軸の公転の様子をイメージしよう。
まず、夏至と冬至に相当する位置では、自転軸は太陽と天王星を結ぶ線上にあり、また、春分と秋分に相当する位置では、自転軸は太陽と天王星を結ぶ線と直交する。
このため、夏至と冬至に相当する位置では、南半球と北半球が完全に昼と夜とに分かれる。自転軸が横倒しになっているから自転してもそれは変わらない。毎日が昼であり、夜である。春分と秋分に相当する位置にあるときは、南北両半球に自転とともに均等に昼と夜が訪れる。この昼だけ・夜だけ状態と、昼夜が均等に訪れる状態の間の期間は、各々の状態の混合となる。
太陽から遠い天王星は、四万二六〇〇日以上をかけてやっと一公転する。したがって、昼だけ・夜だけ、昼夜均等、そして各々の状態の混合といった季節のリズムが、ごくゆったりとしたペースで繰り返されるわけだ。
横倒しでごろごろ転がるように回る天王星は、惑星の中では一番のひょうきん者である。横倒しになってしまったのは、直径がその半分ほどもある巨大な微惑星が、原始天王星に衝突したからだといわれている。
* 厳密には不変ではない。十分に長い時間スケールでみれば少しずつ方向を変えている(第1章の12参照)。
17.冥王星は惑星なのか?
冥王星の“惑星”としての地位がゆらいでいる。その一つの根拠は、冥王星は他の星とパートナーを組む連星ではないのかというもの。他の星とは、一九七八年に発見されたカロンである。この星が冥王星の衛星なのであれば冥王星は惑星といえるかもしれないが、連星であれば冥王星だけを惑星というわけにはいかなくなる。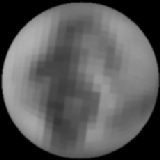
連星というのは、互いの引力に引かれ合って、共通の重心のまわりを公転する複数の星のことである。この共通重心の位置は重い星側に偏る。このため、重い星の公転はほとんど目立たず、軽い星の公転だけが目につくようになる。これがあんまり極端だと、軽い星は重い星の衛星といったほうがよくなる。月と地球がちょうどそんな関係だ(第1章の11参照)。
しかし冥王星の場合は、カロンがあまりにも大きすぎるのである。カロンの直径は冥王星の半分もあり(月の場合は地球の四分の一)、しかも冥王星からわずか一万七〇〇〇kmのところを、約六・四日の周期で公転している。このことから、カロンは衛星というよりも、冥王星の連星といったほうがいいだろうという見方が出てくるわけだ。もしそうならば、冥王星は単なる惑星ではなく、連惑星といったものになる。
冥王星の惑星としての地位をゆるがすもう一つの根拠は、冥王星は大きな小惑星か流星であるとする見方や、カイパー・ベルト(次項参照)に属する巨大な彗星だとする見方があることだ。事実、冥王星の軌道は他の惑星とは大きく異なり、流星や彗星のそれに近い。約二四八年という長い周期で公転し、他の惑星の軌道と一七度も傾き、近日点(太陽からの距離が四四億km)と遠日点(同七四億km)とのずれが極端に大きい。近日点では海王星の軌道よりも内側に入ってしまう。現在がまさにそうで、一九九九年までこの状態がつづく。
このように、冥王星についてはいろいろにとりざたされるが、それも結局は、この星がまだよく知られていないからだ。あまりにも遠くて小さい(月の約六七%)ために、あのハッブル宇宙望遠鏡ですら観測するのがむずかしい。探査機が訪れていない唯一の惑星でもある。NASAでは、二〇〇六年の冥王星近接探査を計画しているが、打ち上げは一九九九年だという。この時期をのがせば、冥王星は海王星軌道の外側に出てしまうから最後のチャンスだ。
ところで以前、冥王星の外側の軌道を回る天体が発見され、「一〇番目の惑星発見か?」と話題になったことがある。その後も発見はつづき、その数は一〇個以上にもなった*。ただ、これらの星は直径が一〇〇~二〇〇km程度しかなく、惑星というにはあまりにも小さすぎた。火星と木星の間にある小惑星帯のケレスですら一〇〇〇km近くある。冥王星は、二三二〇kmだ。最低でも二〇〇〇km以上はないと、惑星扱いにはしてもらえないのである。
* 海王星軌道以遠(冥王星の外側も含む)に範囲を広げると、このような天体はすでに三〇個以上見つかっている。カイパー・ベルト天体(次項参照)と考えられている。
18.太陽系の放浪者、彗星
彗星はほうき星とも呼ばれ、古代から知られていた。中国には、紀元前二四〇年にまでさかのぼるハレー彗星の記録がある。
彗星の起源についてはさまざまな考えがあるが、大別すると次の3つがある。
1.恒星間起源説
恒星間を漂うダストの表面に氷が凝着し、それらが集まって彗星核になる。
2.オールトの雲起源説
オールトの雲とは、一兆個かそれ以上の彗星(氷の塊)の群れからなる天体で、太陽から三万天文単位*1のところ(冥王星軌道のはるか外側)を公転していると考えられている。全体の質量は木星程度だ。太陽系が形成された際に、何らかの理由で惑星になりそこなった微惑星(第1章の2参照)の群れが、外側の巨大惑星(木星など)の引力に引っ張られ、加速スイングバイ(第5章の4参照)をして、太陽から遠いところに放り出されたものだとされる。このオールトの雲と太陽との引力のバランスが何らかの理由で崩れると、雲に含まれる一部の彗星が太陽に引きつけられて、太陽のまわりを公転するようになるという。
3.カイパー・ベルト起源説
カイパー・ベルトとは、太陽から三〇~一〇〇天文単位のあたり(海王星軌道以遠)を公転している帯状の天体である。たくさんの彗星でできており、直径が一〇〇kmを超すような大きな彗星も、三万五〇〇〇個くらいあると推測されている。もともと太陽から遠く、外側に巨大な惑星がなかったために、オールトの雲のように引きつけられて遠くへ飛ばされることはなかった微惑星の群れだと考えられている。これに含まれる彗星が太陽の引力に屈すると、太陽のまわりを公転するようになるわけである。
彗星というのは、水やガスの凍ったものとチリとの混合体である。このため、汚れた雪だるまとか、凍った泥の玉とも呼ばれる。この彗星が太陽に近づくと、太陽から吹きつけている太陽風の影響を受けて氷やチリを昇華*2させる。このときにできる気体が、太陽風の圧力で太陽とは反対方向に吹き流される。これが彗星のシッポだ。彗星と混同しやすい流星(流れ星)は、氷の塊ではなく隕石である。この隕石が地球の引力にとらえられると、大気との摩擦で燃焼し、発光するわけだ。燃えつきずに地上に落下するものもある。
彗星で有名なのは、何といってもハレー彗星である。平均周期は七六年で、最近では一九八六年に地球に最接近している。次の最接近は二〇六一年だ。一九九四年七月に、木星に衝突したことで知られるシューメーカー・レビー第九彗星(写真参照)は、一九九三年に発見された短周期彗星である。また、今世紀最大の彗星として話題を呼んだヘールボップ彗星は、一九九五年に発見され、一九九七年四月に太陽に最接近した。次の最接近は二四〇〇年後だという。そして、一九九六年一月に鹿児島県のアマチュア天文家の百武祐司さんが発見した百武彗星は、同年三月に〇・一天文単位にまで地球に大接近し、肉眼でもよく見えた。周期は一万四〇〇〇年だという。
オールトの雲やカイパー・ベルト起源の彗星は太陽系の星だが、恒星間起源の彗星は太陽系の星ではない。周期の異常に長い百武彗星は、恒星間起源の彗星だと考えられている。
*1 一天文単位は地球と太陽間の距離で、約一億五千万km。
*2 固体から液体にならず直接気体になること。
19.太陽系のオデッセイ、ボイジャーの旅はいつまでつづく?
ボイジャーには面白いエピソードがある。ボイジャーがまだ軌道設計の段階にあったとき、ボイジャーが飛行する様子をコンピュータ・グラフィックスで見せられたアメリカの国会議員たちは、その素晴らしさに大いに感動して、当初は土星までしかなかった予算を、海王星まで増額したという。
木星以遠の惑星探査に活躍したボイジャーには1号と2号があり、1号は一九七七年九月五日、2号は同年八月二〇日に打ち上げられた。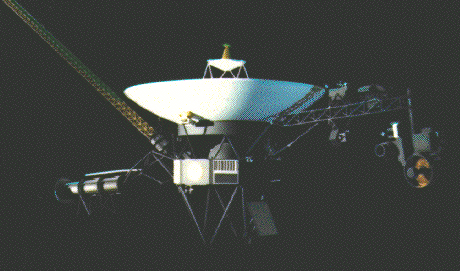
ボイジャー1号は、一九七九年に木星、八〇年に土星に接近した。このとき、最適な軌道を選んでやれば冥王星へ向かうことも可能だったが、NASAは、冥王星の観測を行なう代わりに土星の衛星タイタンに接近して観測するほうを選んだ。太陽系で二番目に大きい衛星タイタンは、太陽系の衛星で唯一大量の大気をもつ星として知られていたからで、ボイジャー1号は、その大気の大半は窒素であって酸素はないこと、核酸の素材であるシアン化水素がごく微量含まれることなどを明らかにした。こうして、タイタンに生命体が存在するごくかすかな可能性を私たちに伝えたのち、ボイジャー1号は軌道を大きく変えて太陽系外へと向かった。
一方、ボイジャー2号は、1号と入れ違いに木星と土星に接近したあと、一九八六年に天王星、八九年には海王星を訪れた。海王星は地球から隔たること四三億kmの彼方だ。その衛星トリトンはマイナス二三五度の凍った星だが、ボイジャー2号はその星に液体窒素を噴き上げる冷たい火山を発見し、その星が生きていることを証明した。そしてそれを置き土産に、ボイジャー2号も太陽系をあとにした。
ボイジャー2号がなぜ四三億km彼方の海王星にまで行けたかというと、ボイジャー2号は、地球の引力圏を脱したあとは、行く先々の惑星の引力を推進力として利用し、慣性で飛行をつづけたからだ*。このためには綿密な軌道計算と最適な惑星の配列が必要だったが、うまい具合にボイジャー2号は、一八九年に一度しかないという絶妙の惑星配列のチャンスに恵まれた。
太陽系外へと旅立った二機のボイジャーは、原子力電池をだましだまし使いながら、二〇三〇年頃までは地球とのきずなを保ちつづける。姿勢制御も可能だ。地球出発以来、足かけ五三年にも及ぶ旅である。だがそのあとは、電力が不足して正常に機能しなくなる。二機のボイジャーは、暗黒の宇宙空間をさまようただのチリとなってしまうのだ。
* スイングバイ航法という(第5章の4参照)
<コラム>
世紀末の星空は、夢で明るい。
宇宙好きにとって、一九九八年はアポロ以来の胸おどる年になった。まず一月にはNASAが、人類が最後に月に降り立ったアポロ一七号から二五年ぶりとなる月探査機を打ち上げた。無人探査機だが、月のまわりの軌道を少しずつずれながら周回し、初めて月面全体を観測する。将来の月面基地建設に必要な各種データを一年間にわたって収集するが、ハイライトは月面に氷があるかどうかだ。
一一月には、宇宙ステーションのモジュールを積んだロシアのプロトンロケットが打ち上げられ、国際宇宙ステーション(第5章の8参照)の建造がスタートした。次はスペースシャトルがその任を果たす。年内四回をはじめ、二〇〇三年の完成までに計四五回打ち上げられるという。
船外活動によるステーションの組み立てには、日本人宇宙飛行士の若田光一さんが加わるが、日本人初の船外活動をした土井隆雄さんや、新規採用された日本人宇宙飛行士も活躍するだろう。99年には米国とロシアの宇宙飛行士が実際に住み始める。
夏は日本の出番であった。文部省宇宙科学研究所がついに火星探査機「プラネット-B(のぞみ)」を打ち上げた。日本初の惑星探査機で、火星到着は四年後だ。また年末には、同省国立天文台が一六年をかけて構想し、設計した世界最大級の天体望遠鏡「すばる」が、ハワイのマウナケア山頂に完成した(第2章のコラム参照)。
秋には、日本人初の女性宇宙飛行士である向井千秋さんが、スペースシャトルで再び宇宙へ飛び立った。無重力下で海水魚ガマアンコウを使った実験を行い、最年長宇宙飛行士であるグレンさんの主治医もつとめた。
世紀末は、地上のいやなことは忘れ、夢で明るい星空を仰ごう。
|