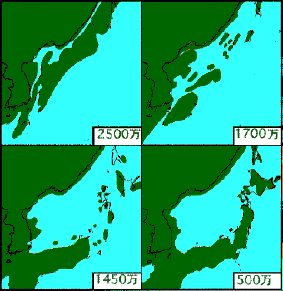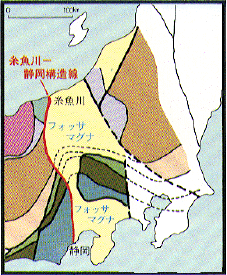|
第1章 地球の謎に迫る(2)
11.海の満ち干きはどうして起こるのか?
12.北半球と南半球の季節が逆になるのはなぜ?
13.異常気象の原因は何か?
14.大陸移動の生き証人,大西洋
15.地震が太平洋岸に多いワケ
16.海が干上がらなかったのは、大陸ができたおかげ
17.日本列島誕生秘話
18.地球温暖化は防げるのか?
19.なぜフロンガスは、戻らないブランコといわれるのか?
20.酸性雨で,髪の毛が赤や緑や黄色になる?!
21.地球の危機を救うか、バイオテクノロジー
<コラム>
究極の製薬工場、クローン動物
12.北半球と南半球の季節が逆になるのはなぜ?
答えをズバリいうと、地球の自転軸が公転面に対して垂直になっていず、二三・五度ほど傾いているからだ。四季があるのも、この傾きのおかげである。太陽系の惑星は、水星をのぞいてすべて自転軸が傾いている。金星などは一八〇度近く傾いているために、自転の向きが反転してしまっている。
自転軸に傾きが生ずるのは歳差運動による。コマが倒れそうになると軸がブレながら回るが、あれと同じ運動だ。このブレが自転軸の傾きとなって現われる。
コマの場合だと、回転軸の傾く方向は回転とともに刻々と変わる。ところが星の場合、歳差運動の周期が極度に長いために(地球の場合二万六〇〇〇年)、人間の時間スケールからすると自転軸の傾く方向は変わらないように見える。
自転軸の両端の一方の端がその星の北極、他方の端が南極であるが、北極側において自転軸が指す方向に浮かぶ目印となる星のことを北極星という。この北極星は、星の自転軸の歳差運動にともなって変わる。地球の場合、現在の北極星はこぐま座のアルファ星だが、一万二〇〇〇年後にはこと座のベガに変わることがわかっている。
さて、本題の北半球と南半球の季節がなぜ逆になるかだが、それを知るにはまず、四季がなぜ生ずるのかを知る必要がある。これらの原因となっているのは前述したように惑星の自転軸の傾きだが、その傾く方向は公転しつつもつねに不変である。軌道上のある特定の位置にあるときには、自転軸は太陽に向かっておじぎをし、その真向かいの軌道上にあるときには太陽に向かってそっくり返り、その中間点の2ヶ所にあるときには、太陽に向かっておじぎもそっくり返りもしないニュートラルな状態となる。おじぎをするときは、北半球のほうが太陽により近くなるので夏(夏至)となり、南半球は太陽からより遠くなって冬(冬至)となる。ふんぞり返るときはその逆で、ニュートラルな状態にあるときは春分ないしは秋分である。
13.異常気象の原因は何か?
異常気象の主な原因としては次の三つが考えられる。
①排出二酸化炭素による温室効果
②大規模な海流異常
③大規模な火山噴火
この中で人間が原因となっているのが①だ。過剰な温室効果により地球が異常に温暖化する。最近のカラ梅雨や早すぎる猛暑のような季節リズムの変調は、おそらくどんどんひどくなる温暖化の影響であろう。この温暖化については、本章の18で改めてとりあげるので、ここでは②と③について解説しよう。
まず大規模な海流異常だが、これの有名なのがエルニーニョ現象だ。ペルー沿岸から日付変更線(本章の9参照)にかけての広い海域に起こる海流異常で、これにより海面水温が数度上昇する。数年ごとに、半年から一年半の間、大規模に発生する。
エルニーニョは、アンチョビの不漁などをもたらしてペルー経済に大きな打撃を与えるだけでなく、世界各地の異常気象の原因ともなっている。その例をあげていこう。
一九八二年から翌年にかけて発生した今世紀最大のエルニーニョは、アフリカ、インド、オーストラリアに干ばつをもたらし、日本にも冷夏暖冬をもたらした。また一九九〇年に発生したエルニーニョは、九一年に南アフリカで起こった今世紀最悪の大干ばつの原因となり、一八〇〇万人もの人々に深刻な食料危機をもたらした。また、アメリカのフロリダ州ではハリケーンも起こった。
ニューヨークの大寒波も、どうやらエルニーニョが原因らしい。九三年にコメの大凶作をもたらした日本の冷夏の原因の一つにもあげられている。こうなると、悪いのは何でもかんでもエルニーニョといった感がある。
タイ米騒動まで引き起こした九三年の日本の冷夏は、九一年に起こったフィリピンのピナツボ火山の大噴火も原因の一つとされる。山頂が吹き飛んで雲を突き抜け、成層圏にまで噴煙が吹き上がったという今世紀最大規模の大噴火だ。噴煙は成層圏を漂って世界中に広がり、日光をさえぎって日照不足や異常低温をもたらした。これが二年後、日本をも襲ってコメの大凶作を引き起こしたというわけだ。
14.大陸移動の生き証人、大西洋
二億年前頃の地球には、一つの超大陸「パンゲア」と海洋だけがあった。そのパンゲアは、マントルに溜まった熱の放出をさまたげたために、あちこちが引き裂かれるにいたった(本章の5参照)。
この大陸分裂の面影を今に残しているのが大西洋だ。大西洋を縦断する中央海嶺は、一億年前頃にリソスフェア(後述)に生じた裂け目の名残りなのである。その裂け目から始まった活動によって、それまで一つであった南米大陸とアフリカ大陸が切り離され、そのあとに海水が浸入して大西洋ができたのだ。大西洋の地図でジグソーパズルをやってみれば、それはすぐにわかる。このパズルがただの遊び事ではすまされないことに初めて気づいたのが、大陸移動説の創始者、あのウェゲナーだ。一九一二年のことである。しかし、このあまりに破天荒なアイデアは当時では受け入れられなかった。失意のウェゲナーは、一九三〇年、グリーンランド探検の途上でその不遇の生涯を閉じた。
現在では大陸移動説を疑う人はほとんどいないが、それはプレートテクトニクスという理論が確立されているからである。その理論のあらましはこうだ。
地球のいちばん外側を覆っている地殻は、海底であったり陸地であったりするが、この地殻をのせているのはリソスフェアという硬い岩石からなる層で、リソスフェアの下にはアセノスフェアという溶融した岩石からなる層がある。
二億年前頃、パンゲアが引き裂かれたのは、パンゲアをのせていたリソスフェアがマントルに溜まっていた熱エネルギーの暴発のために引き裂かれたせいだった。このとき、アセノスフェアの溶融岩石はリソスフェアの裂け目を涌き上がり、一部は地表にまで達して固まった。幼い地殻の誕生である。地表まで達しえなかった溶融岩石は、新たに次々と湧き上がる溶融岩石の外側を沈降していくが、途中で冷えて固まり、裂け目の両側に新しいリソスフェアを形成した。
果てしなくつづくこの涌き上がりと沈降によって、裂け目の両側の新しいリソスフェアと、その上を覆う幼い地殻とは少しずつ成長していった。一方、引き裂かれて分裂した古いリソスフェアとその上にのっかった大陸片どうしは、成長する新しいリソスフェアに押されて、互いに遠ざかっていった。そしてそのあとには海水が侵入し、大西洋が誕生した。
新しいリソスフェアと、その上にのっかった海底地殻の成長はとどまることなくつづき、やがては広大な面積をもつプレートとなった。このプレートの絶え間ない成長によって、大西洋はいま見るような大洋となったわけである。プレートはまだ成長しつづけているので、南米大陸とアフリカ大陸とは、現在も互いに遠ざかりつつある。
15.地震が太平洋岸に多いワケ
太平洋は、超大陸「パンゲア」の誕生以前からあった原始の海である。このため、太平洋のプレートテクトニクスは、大西洋のものとはかなり趣きが異なる。
プレートテクトニクスとは、その名が示すように、プレートのダイナミクスを明らかにした理論だ。プレートとはリソスフェアのことと思えばよい。大陸地殻がのっかったリソスフェアを大陸プレート、太平洋のような原始の海をのせた海底地殻がのっかったリソスフェアを海洋プレートと呼ぶ。
大西洋は大陸プレートに分類される。なぜなら、大西洋の海底地殻をのせたリソスフェアと、そのリソスフェアの拡大によって動かされている古いリソスフェア(南米大陸とアフリカ大陸がのっている)とは、新旧の差はあっても構造的には一体だからだ(前項参照)。
大西洋に中央海嶺(大陸分裂の裂け目)があるごとく、太平洋にも中南米はるか沖合いに東太平洋海嶺が存在し、新しいリソスフェアを絶え間なく生成してプレートを拡大させている。東太平洋海嶺の西側に広がる海洋プレートを太平洋プレート、東側に広がる海洋プレートをナスカプレートという。
拡大する海洋プレートが大陸プレートと接する境界においては、海洋プレートが大陸プレートに沈み込んだり、プレートどうしがすれ違ったりする。沈み込むのは、海洋プレートが大陸プレートを押す形となる場合で、海洋プレートは大陸プレートよりも密度が高くて重いために沈み込むわけだ。この沈み込みが起こるところを海溝という。
海洋プレートの沈み込みは、ひずみエネルギーとなって大陸プレートに蓄積される。そして、このエネルギーが暴発すると、地殻に断層を生じさせたり、すでに存在する活断層をずらせたりするので地震が起こる。すぐ間近で海洋プレートが沈み込む日本やチリなどに地震が多いのはこのためだ。
また、プレートどうしのすれ違いもひずみエネルギーを生じさせるから、地震の原因となる。太平洋プレートと北米プレートとがすれ違うサンアンドレアス断層がその例だ。この活断層は、アメリカからメキシコにかけての太平洋沿岸内部にある。何と、海沿いの内陸部でプレートがすれ違っているのだ。地震が起こるのもむりはない。一九九四年にはサンフランシスコ大地震を発生させた。このような、内陸部に存在する活断層が震源となって起こる地震を直下型地震と呼ぶ。あの阪神大震災も直下型地震だ。淡路島側の野島断層と神戸側の六甲断層系が震源となった。
これでわかるように、プレートの沈み込みやすれ違いが常時起こっている太平洋は、ちっとも太平じゃないわけだ。これに対して、大陸プレートの上にある大西洋とその沿岸一帯には地震はほとんどない。

※上図は内閣府防災情報のページより引用
16.海が干上がらなかったのは、大陸ができたおかげ
原始地球に海が誕生したあらましは本章の3で述べたが、実はこの海は、大陸がなかったら干上がっていただろう。大陸が、過剰な温室効果をやわらげてくれたために、海が存続できたのである。
本章の4でも述べたように、太古の地球にできつつあった海底地殻は、まだ固まりきっていない高熱のマントルの対流のために、絶えず移動していた。そして、海底地殻があまりに厚くなるとその重さのためにマントルに沈み込んだ。その一方で、マントルのマグマは、海底地殻の薄いところを涌き上がり、海底火山を形成した。
大気の大部分を占める二酸化炭素は海中に溶け込み、海中のマグネシウムやカルシウムなどの炭酸化合物と結合して、石灰岩などの炭酸塩岩となった。海中に存在する炭酸化合物は、海底火山を涌き上がるマグマ物質(ケイ酸塩類)と海水とが反応して形成されたものだ。
炭酸塩岩は海底に沈澱し、海底地殻の上層部を形成した。やがて海底地殻が厚くなり重くなってマントルに沈み込むと、炭酸塩岩は熱で分解されて二酸化炭素と炭酸塩とに分離した。炭酸塩はマントルに溶け込んだが、二酸化炭素は火山ガスとなって再び地表へ噴出していった。このような二酸化炭素の循環のために、大気中の二酸化炭素はなかなか減少せず、これが原因で温室効果もそれほど弱まることはなかった。
海の誕生とともに成長しつづけていた陸地は、三八億年前頃には大陸と呼びうるほどの規模になっていた。マントル対流にのって移動する海底地殻がこの大陸にぶつかると、海底地殻は陸地よりも重いために陸地との境界でマントルに沈み込んだ。このとき、海底地殻の上層を形成する炭酸塩岩は陸地に削りとられ、陸上にせり上げられた。この状態がつづくことによって、マントルに沈み込む炭酸塩岩の総量が減っていき、二酸化炭素の循環が抑制された。また、大陸自身も雨を吸収することで、雨に溶け込んでいる二酸化炭素を吸収した。こうして大気中の二酸化炭素は徐々に減少していき、それにともなって温室効果も弱まっていった。
マントルはやがて冷えて固まり、リソスフェアとアセノスフェアも形成された。また、海底火山の規模の大きなものはそのまま海嶺となって、アセノスフェアの溶融岩石を涌き上がらせた。壮大なプレートテクトニクスの幕開けである(前項参照)。
17.日本列島誕生秘話
二五〇〇万年前以前には、日本列島はまだ存在しなかった。ユーラシアプレートという、世界最大の大陸プレート上の地殻の東端の一部を占めるにすぎなかった。あるとき、その東端の地殻に縦方向に裂け目が生じ、それはだんだん広がっていった。やがて水が溜まって、裂け目は縦に細長い湖となった。裂け目はさらに広がり、とうとう海に通じた。裂け目の拡大は一五〇〇万年前頃までつづき、ついに陸塊が完全に切り離されて現在の日本海となった。
日本海によって切り離された陸塊は大小さまざまな島となり、それらの島々の中にはその後に生じた地殻変動によって合体したり、大陸とつながったりするものもあった。そして、北から延びているオホーツクプレート(北米プレート)上の海底が隆起して陸地ができると、その陸地とも合体した。その合体跡が、フォッサマグナと呼ばれるベルト地帯だ。幅約一〇〇km、長さ三〇〇kmにわたって本州の中央部を横切る。ナウマン像の化石の発見で知られるドイツ人地質学者ナウマンが、明治時代に見つけた。
このようにして日本列島の基本構造が少しずつできあがっていき、五〇〇万年前頃にはほぼ現在の日本列島らしくなった。
ここで面白いのが伊豆半島だ。この半島は何とはるか東南の海から運ばれてきて、五〇万年前頃に本州にぶつかったものらしい。運んだのは、フィリピン海プレートという海洋プレートだ。
海洋プレートが拡大している状態とは、いってみればベルトコンベアが動いているようなものである。プレートに島がのっていれば、その島はやがて、プレートが沈み込む海溝まで運ばれて大陸プレートにぶつかる。フィリピン海プレートは、日本の西南部沖でも沈み込んでいるので、そのプレートによって運ばれてきた“伊豆島”が本州へぶつかって伊豆半島となり、間にあったかつての海が盛り上がって足柄山地になった。インド大陸がユーラシア大陸にぶつかって、ヒマラヤ山脈をつくったのと同じ理屈だ(本章の5参照)。フィリピン海プレートよりもずっとでかい太平洋プレートも、銚子沖の日本海溝で沈み込んでいるから、あのハワイもやがては日本にぶつかるかもしれない。
プレートテクトニクスはまた、アフリカ大陸の東縁が遠い将来に切り離されることも予言している。数十万年後、あるいは数百万年後の世界地図は、現在とはだいぶ異なったものになっているだろう。人類がそれまで存続しているかどうかはわからないけれど・・・。
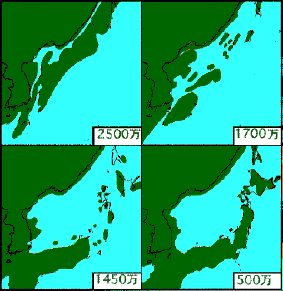 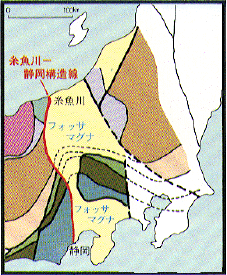
図は2点とも糸魚川市のHP「糸魚川市の紹介−糸魚川の歴史」(http://www.ojas.co.jp/itoigawa/syoukai/rekishi.html)より引用
18.地球温暖化は防げるのか?
地球を温暖化させている元凶は大気中の過剰な二酸化炭素だ。二酸化炭素は熱エネルギーを吸収する性質があり、これが地上からの放熱をさまたげて温暖化をもたらすのである。この作用を温室効果というが、温室効果をもつ気体は実はほかにもある。メタン、フロン、一酸化炭素、地上オゾンなどの気体がそうだ。ただ、これらの気体にくらべて二酸化炭素の量が圧倒的に多いので、二酸化炭素が温室効果の元凶とされているのである。
大気中の二酸化炭素を増やしている二大要因は、化石燃料の燃焼と森林破壊だといわれている。ただし、森林破壊による二酸化炭素の増大というのは、その実態が誤解されている面がある。森林破壊というとつい森林の“伐採”をイメージしがちだが、実は、二酸化炭素を増大させている森林破壊とは、森林を焼くことなのである。熱帯雨林の保有国は一般的に貧しく、しかも人口増加が著しい。そこで、食料増産のために森林を焼き払って農地や放牧地を確保している。この燃焼によって放出される二酸化炭素の量は、一説によれば、化石燃料によって生じるそれの約半分近くになるという。つまり、森林そのものが燃焼によって二酸化炭素を出しているのである。この二酸化炭素の量は、焼き払われた森林がもし焼かれなければ吸収したであろう二酸化炭素の量をはるかに上回る。
森林が実際に二酸化炭素を吸収するかどうかも、古い森林にかぎってはかなり微妙である(本章の8参照)。森林に棲息する微生物や菌類が消費する以上の酸素を放出し、それと同量の二酸化炭素を吸収できるのは若い森林なのだ。森林の破壊をくい止める一方で、若い森林を増やす努力をすべきだろう。
ところで、世界中で排出されている二酸化炭素の量からはじいてみると、地球の気温はもっと上がっているはずだという。とすると、森林以外の何物かが、膨大な量の二酸化炭素を吸収してくれていることになる。それは、海だ。
海がもつ二酸化炭素の巨大な吸収作用に注目して、いま、ユニークな計画が浮上している。回収した二酸化炭素を液化して、深海の底に埋めてしまおうというものだ。液化した二酸化炭素は水圧でシャーベット状となり、魚などの死骸からできた炭酸カルシウムと中和して、無害な炭酸塩岩に変わる(本章の16参照)。火力発電所など、二酸化炭素の回収が比較的容易なところでの導入が検討されている。
また、海洋に棲息する植物プランクトンや藻類がもつ光合成能力を増大させる研究もなされている。これらの光合成生物の生育に必要な栄養源を海面に散布するか、海流や海底ダムを利用して海底に眠っている栄養源を海面に浮上させるかして、海面付近を生活圏とする光合成生物の数を増やし、大気中の二酸化炭素をより大量に吸収させようとするものだ。
19.なぜフロンガスは、戻らないブランコといわれるのか?
地表を覆う大気は、地上から一〇kmぐらいの高さでは対流を起こしている。この層を対流圏という。そしてその上、地上から五〇kmぐらいの高さまでを成層圏という。この成層圏の地上から三五〜四〇kmあたりに漂う酸素は、太陽の紫外線を浴びて化学反応を起こし、酸素原子が三つくっついたオゾンの層となる。これがオゾン層である。
オゾンは、ごく微量ではあるが私たちの周辺にも存在する。森の中を歩いているときとか、落雷時やコピー機の使用時などに、かすかにその匂いを体験するときがある。
オゾンには悪玉と善玉の二面性がある。悪玉としては、車の排ガスと反応して光化学スモッグを発生させたり、ゴム製品を劣化させたりする。また善玉としては、殺菌、漂白、脱臭などに効力を示す。
オゾン層の破壊はなぜいけないかというと、それが地球生物に異変をもたらすからである。オゾン層は、波長の短い高エネルギーの紫外線を吸収して、無害な熱エネルギーとして放出している。高エネルギーの紫外線がもし、そのまま地上に降りそそげば、生物の細胞に異変が生じ、DNAが破壊されたりする。皮膚ガンや白内障の原因にもなる。X線の弱いやつを浴びているようなものなのだ。オゾン層がなければ、地球の生物は昼間は外に出られないであろう。
このオゾン層が何と破壊されていることが判明した。その主犯はフロンだった。フロンというのは、一九二八年に初めて人工合成され、一九六〇年代以降の有機化学工業の発展にともなって大量消費されるようになった物質だ。人畜無害なものとして、スプレーの噴射剤、冷蔵庫やエアコンの冷媒、精密機械の洗浄剤などに用いられた。
フロンは零下三〇度近くにならないと液化しないガスで、それが大気中に放出されると、少しずつ上昇していって成層圏にまで入り込み、オゾン層に達する。そして、オゾン層に降りそそぐ高エネルギーの紫外線を浴びて分解し、オゾンと化学反応を起こす。これによってオゾンも分解し、元の酸素に戻ってしまう。この化学反応の主役はフロンの形成物質の一つである塩素だが、この塩素一個で一〇万個のオゾンが破壊されるという。
オゾンが破壊されて、オゾン層にぽっかり開いた穴をオゾンホールという。オゾンホールは今のところ極地の上空にだけできる。南極のほうが圧倒的にでかい。最大で南極大陸の一・八倍くらいに達する。それもどういうわけか、九、一〇、一一月にかぎってできる。
地上で放出されたフロンが、オゾン層に達するまでには平均二〇〜三〇年かかるという。つまり、いまオゾン層を破壊しているのは、二〇〜三〇年前に放出されたフロンなのだ。人類は、今世紀中にフロンの生産を全廃することを国際間でとり決めたが*、すでに放出されたフロンの八〇%は、まだ対流圏をさまよっている。これによるオゾンの破壊は、今後、何一〇年にもわたってつづく。戻らないブランコといわれる由縁である。
* フロンの仲間に、オゾン層の破壊力はフロンの一〇倍といわれる特定フロンがあるが、この特定フロンの生産は一九九五年に全廃することが議決されている。
20.酸性雨で,髪の毛が赤や緑や黄色になる?!
TVのアニメ番組に出てくるキャラクタの髪の色は、ちゃんと日本人の名前がついているのに、どういうわけだか赤や緑や黄色(金髪?)だったりする。
でも、へたをすると、これが現実となる可能性もないわけではない。人類の髪の色が赤や緑や黄色に変色する。ファッショナブルというか、気持ち悪いというか・・・。
犯人は酸性雨だ。金とプラチナ以外は何でも溶かしてしまう酸の混じった雨である。この酸性雨が土に染み込んで地下水を酸性化し、その地下水が水道管の銅を溶かし、その銅の混じった地下水を使って洗った髪が、銅の緑青に染まって緑色になったりするわけだ。この伝でいけば、鉄サビの溶けた水で洗えば髪は赤色に、真鍮の溶けた水で洗えば金髪に、アルミニウムの溶けた水で洗えば銀髪になる?!
地下水で洗った髪が緑色に染まったという話は、一九八〇年頃にスウェーデンで本当にあった事件である。その地下水を飲んだ者は下痢に苦しめられたという。
酸性雨の被害の報告をつづけよう。古いところでは、一九五二年にロンドンで殺人スモッグ事件というのが発生した。このときに降った酸性雨は胃酸なみの強烈さで、その雨が霧となって大気中に居座ったために、実に四〇〇〇人あまりが死亡した。一方、北欧やカナダでは、一九六〇年あたりから異常に澄んだ一見静かで美しい「死の湖」が急増した。酸性雨により湖沼の酸性度が上がり、魚などのすべての水棲生物が死滅してしまったのが原因だった。そのほかにも、森林が立ち枯れしたり、歴史的な建造物や彫像が溶け出したり、鉄道のレールが溶けたりと、その被害は枚挙にいとまがない。
なぜ、雨に酸が混じるのだろう。それは、火力発電所、工場、車、飛行機などから排出される排ガスに含まれる硫黄酸化物や窒素酸化物が、大気中で紫外線エネルギーなどによって化学変化を起こし、硫酸や硝酸となって雨や雪にとり込まれるからだ。
排ガスは当然、先進国のほうがたくさん出すはずだが、意外や、中国や東南アジアなどの発展途上国も負けず劣らず出している。とくに中国は、石炭を多用するために硫黄酸化物をいっぱい出す。これが大気圏を数千kmも旅をして、日本などに酸性雨を降らせるのだ。
地球温暖化やオゾン層破壊もそうだが、地球環境の破壊と汚染は、もはや国家レベルでどうにかできる問題ではなくなっている。世界中の一人ひとりが、車の利用を減らすとか、電気の使用を減らすとか、有害なガスを出すゴミを出さないとかいった「低エネルギー消費生活」を実践するほかないようなところにまできている。
21.地球の危機を救うか、バイオテクノロジー
環境汚染、エネルギー資源の枯渇、土壌の砂漠化、食料不足などなど、生き物にとっての地球はいま、危機的な状況にある。これを救う技術として、バイオテクノロジーが改めて注目されている。バイオテクノロジーを利用したプロセスは常温・常圧で反応が進むし、副産物をほとんど生成しない。これは、化石燃料をそれほど必要としないということであり、二酸化炭素もあまり排出しないということである。設備コストも少なくてすむ。
それでは、バイオテクノロジーがいかに活用されているかをみていこう。
まず環境汚染に対しては、廃棄物や排水、排出ガスなどの汚染物質を微生物に分解させるバイオ戦略が進められている。たとえば、ドイツのデュッセルドルフの下水処理場では、下水に含まれる有機物質を微生物に分解させてメタンに変えている。メタンは燃料として活用できるので一石二鳥だ。また排出ガスへの対策としては、ガス中に含まれる汚染物質を微生物に分解させるバイオフィルターが実用化されている。高価な脱硫装置や脱窒装置などを導入することが困難な発展途上国にとっては、このバイオフィルターは大きな福音であろう。バイオテクノロジーを活用した環境汚染対策にはそのほかにも、生分解性のプラスチックや代替フロンなどがある。
バイオマス(植物性廃棄物、未利用植物、海藻、動物の排泄物など)をエネルギー資源として活用するバイオエネルギーも有望だ。たとえば、サトウキビやトウモロコシを発酵させてアルコールをつくり、ガソリンの代用とする。ブラジルやアメリカでは現実に行なわれている。また微生物を使って、バイオマスから水素やメタンなどの燃料ガスを生産する研究も進められている。さらに面白いのは、石油と同等の油成分を生合成する植物(ユーカリなど)や微生物が存在することだ。この油を燃料とする自動車の走行テストも行なわれている。バイオマス資源は再生産がきくので、化石燃料のように資源枯渇の心配がなく、有毒ガスもあまり出さない。
現在もっとも注目されているバイオテクノロジーはといえば、やはり遺伝子工学であろう。乾燥や疫病に強い品種の植物が遺伝子工学によって生み出されれば、砂漠の緑地化や農産物の増産に役立ち、食料不足の解消にも貢献する。また、乾燥地帯に特有の高塩性土壌に適応する耐塩性植物や、体内に入った除草剤を分解して無害なものにする無毒化植物なども、遺伝子工学を使って開発が進められている。
バイオテクノロジーは環境モニタリングの分野でも成果をあげている。生体材料のもつ優れた分子識別能力を活用するものだ。窒素酸化物、農薬、発ガン物質、毒物、河川の汚染などを検出するバイオセンサがすでに開発され、実用に供されている。
<コラム>
究極の製薬工場、クローン動物
地球の謎にはあまり関係ないかもしれないが、本章の21の続編といった感じで読んでほしい。
ここでいわんとしているのはもちろん、あのクローン羊「ドリーとポリー」である。イギリスのロスリン研究所と、薬剤製造ベンチャーPPLとの共同研究による成果だ(写真はドリーちゃん)。
クローン羊とは、遺伝子の親にあたる羊から取り出した細胞の核(遺伝子が格納されている)を、代理母の羊から取り出した未受精の“核抜き”卵細胞に融合し、培養して細胞分裂の発生を確認してから、その卵細胞を代理母の体内に戻すことによって作出されたものである。一頭の親の遺伝子をそっくりそのまま受け継いでいるので、クローン羊と呼ばれる。
ドリーとポリーのもっとも大きな相違は、ポリーには、人間の血液凝固因子の第九因子をつくる遺伝子が組み込まれていることである。この第九因子が、ポリーの母乳から出てくることが期待されている。第九因子というのは血友病の治療薬で、従来は献血に頼って生産されていた。ポリーのようなクローンが何頭も作出できるようになれば、第九因子のような人工ではつくり出すことのできない薬剤も確実に大量生産できるわけだ。まさに究極の製薬工場である。
羊以外のクローン動物もすでに登場している。一九九八年一月二〇日、米国マサチューセッツ大学のジェームズ・ローブル博士らは、ポリー型のクローン牛「ジョージとチャーリー」を誕生させたと発表した。薬を大量生産するには、ミルクの産出量の多い牛のほうが有利、というのが博士らのアピールポイントだ。
その後、日本でもクローン牛が作出され、あげくの果てに韓国では、何とクローン人間作出の一歩手前にまでいったという。ある女性から採取した細胞の核を、“同じ女性”からとり出した未受精の核抜き卵子に移植し、細胞の分裂を確認したというのだ。一〇〇%完全な複製人間の誕生も夢ではなくなった。
|