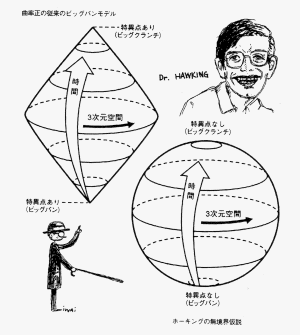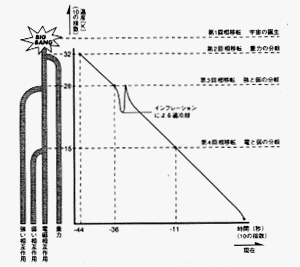|
第2章 宇宙の謎に迫る(1)
1. 最初はからかわれた宇宙開闢ストーリー、ビッグバン理論
2. ビッグバンが残した宇宙の化石とは?
3. ビッグバンは本当に「始まり」なのか?
4. 宇宙の始まりの二大仮説
5. [始まり」を特定する必要のないホーキング宇宙とは?
6. 時間は逆流するか?
7. ただ飯理論といわれるインフレーション宇宙の秘密
8. 宇宙の物質はいかに生み出されたか?
9. 銀河と星の誕生ドラマ
10.星の「死」が生命を「誕生」させた
1.最初はからかわれた宇宙開闢ストーリー、ビッグバン理論
ビッグバン(Big bang)。「バンバン撃ちまくる」とよくいうが、それのどでかい“バン”だ。
ビッグバン理論とは一言でいえば、「この宇宙は、超高圧・超高温の火の玉の出現から始まった」というものだ。アメリカに亡命したロシア人学者、ジョージ・ガモフが一九四八年に唱えた理論である。
ビッグバンという言葉自体は、ガモフ自身が命名したものではないらしい。ビッグバンや膨張宇宙とは正反対の定常宇宙論を唱えるイギリスの名物物理学者フレッド・ホイルが、からかい半分に口にした言葉がそのまま定着したものだという。
ビッグバン理論は、膨張宇宙論から導かれた帰結であった。宇宙が膨張するというのは、アインシュタインの「宇宙方程式」から得られる解である。アインシュタインは、自身が築き上げた一般相対性理論にもとづいて宇宙を記述する宇宙方程式を導いたのだが、この方程式からは、宇宙が変化するという解のみが得られる。宇宙が膨張するというのもその解の一つだ。
アインシュタインは実は、宇宙は静止していなければならないと信じていた。ところが、自分の導いた宇宙方程式からは静止する解が出てこない。膨張か収縮のどちらかになってしまうのである。考えあぐねたすえ彼は、宇宙項(宇宙定数)と呼ばれる項を方程式につけ加えた。こうすると、天体間に働く重力に逆らう反発力が空間に発現し、ある条件のもとでは双方の力が釣り合って宇宙が静止するという解が得られる。
ところが、式の改変の過程の中にとんでもない誤りが発見された。ゼロになるかもしれない式で両辺を割るという、初歩的な誤りが指摘されてしまったのだ。アインシュタインは結局、自分の誤りを認めざるをえなくなり、宇宙項を撤回するはめになった。のちに彼は、ガモフに対して「我が生涯で最大のヘマだった」とこぼしている。
宇宙の膨張を実際の観測で明らかにしたのは、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルだ。守衛出身の素晴らしく優秀な助手の手を借りて夜空を観測し、「銀河のほとんどは私たちから遠ざかっており、遠い銀河ほどその遠ざかる速度は大きい」という事実をつかんだ。当時の観測技術では、距離と遠ざかる速度の双方を観測しうる銀河は二〇個そこそこだった。しかも相当ちらばった観測データだったので、一見しただけではとても、距離と遠ざかる速さが比例しているようには見えない。あえてそう主張したところに、ハッブルの偉大さ(というより大胆さ)があったといえる。
銀河が遠ざかるとはいっても、それは望遠鏡をのぞくとそのように見えるということであって、銀河自体は動いていないことに注意しよう。銀河をとり囲む宇宙空間が膨張することによって、銀河がお互いに遠ざかっているのである。
さて、宇宙が過去からずっと膨張しつづけてきているのなら、宇宙の誕生は膨張がゼロのときでなければならない。このことと現在の宇宙の物質組成に着目して、宇宙の始まりを超高圧・超高温の火の玉の出現として説明したのが、ジョージ・ガモフだったわけである。
2.ビッグバンが残した宇宙の化石とは?
ジョージ・ガモフは、ビッグバン理論を提唱した際、自分の理論の正しさを証明するものとして、あるものの存在を予言していた。そのあるものとは「宇宙背景放射」である。ビッグバンによって放出された光が、今でも宇宙に漂っているだろうというのである。
ビッグバンによって放たれた想像を絶するようなすさまじい光は、宇宙をくまなく満たしたはずである。個々の光はまったくランダムな方向に行き交っている。何かにぶつかったり引き寄せられればそれに吸収されるだろうが、そういうものがなければ四方八方をランダムに行き交うのみである。宇宙の膨張にともなってその光は弱まっていくが、なくなることはない。だからその光は、非常に弱まってはいるだろうが、今でも残っているはずだ。このことをもうちょっと専門的にいうと次のようになる。
光とは、量子論的にいえば、波として伝わっていく空間のひずみと考えることができる。その空間が膨張すれば、光(空間のひずみ)の波長もとうぜん伸びる。したがって現在の宇宙のそこかしこには、ビッグバン当時の光が波長のうーんと伸びた状態(極度の低エネルギー状態)で飛び交っているはずである。その光は、赤外線よりも波長の長い電磁波となっており、その電磁波のエネルギーを熱に換算すると、絶対温度七度くらいとなっているであろう。
以上が、ジョージ・ガモフの予言した宇宙背景放射だ。
一九六五年、この宇宙背景放射はついに発見された。それも偶然にである。ベル電話研究所の二人の研究員がアンテナのテストを行なっていた際、正体不明の電波が捕捉された。あらゆる方向を遮断しても電波は入ってくる。こんな電波は人工的にはつくり出せない。そう結論を下した二人は、その内容をたった二ページの論文にまとめた。その論文を研究所の近くにあるプリンストン大学の宇宙研究グループに見せたところ、それが世紀の大発見であることがわかった。こうしてこの二人、ペンジアスとウィルソンはノーベル賞をかっさらった。たった二ページの論文で。
実をいうと、プリンストン大学の宇宙研究グループも、宇宙背景放射を観測すべく、その資金調達に奔走していたのである。それが、まったく畑違いの研究員によって、発見の栄誉を横どりされてしまった。しかもかの二人は、その後も宇宙論の研究などはやっていない。何とも身につまされるエピソードだ。
この宇宙背景放射の発見によって、ビッグバン理論は、宇宙開闢論の主流を歩み始めることになる。なお、宇宙背景放射の実際の温度は、ガモフの予言した値よりも低く、絶対温度で約三度(マイナス二七〇度)である。これが、現在の宇宙の何もない空間の温度なのだ。
3.ビッグバンは本当に「始まり」なのか?
この宇宙を構成するのは、物質と空間、そして時間である。宇宙の物質とは、星や星間ガスで構成される膨大な数の銀河ということになるが、それらすべての銀河が宇宙に占める割合は、地球の大きさにアリが三匹とも、太平洋にスイカが三個ともいわれるほどに小さい。つまり宇宙はほとんどカラッポなのだ。
また宇宙物質のほとんどは、軽い元素である水素とヘリウムである。水素七、ヘリウム三の割合だという。その他の重い元素はきわめて微量で、全体の三%を占めるにすぎない(本章の9参照)。このことから、銀河というのは全体としてみればとても軽く、宇宙空間にフンワリ漂っている状態なのだ。そして私たちの地球は、その銀河の中の極微のチリとして、銀河全体でたった三%を占めるにすぎない重い元素によって成り立っている星なのだ。
さて、ビッグバン理論というのは、膨張する宇宙と宇宙の物質組成とを、宇宙開闢時にまでさかのぼって検証することを糸口として構築された仮説である。膨張する宇宙を宇宙開闢時にまでさかのぼるということは、宇宙を収縮させていくことである。宇宙を満たすエネルギーの総量が一定であるなら、空間が小さくなるほどエネルギーの密度は大きくなっていき、温度が上昇する*。宇宙開闢時にはそれはピークに達し、宇宙はまさに超高熱・超高圧の火の玉状態となる。元素は壊れ、ばらばらな素粒子の状態になってしまう。
こうした状態から宇宙がスタートしたとすると、大きな運動エネルギーをもつ素粒子どうしは、互いにぶつかり合うだけですぐに離れてしまう。このため、重い元素になるための結合は行なわれにくくなり、結果として構造の簡単な軽い元素で占められる宇宙になったというわけだ。
ところで、このビッグバン理論には大いなる謎がある。超高熱・超高圧の火の玉の出現がビッグバンだとするなら、その火の玉はいかにして生じたのかという謎だ。その火の玉だって小さな宇宙なのではないか。その火の玉自体がもう、すでに膨張をとげた宇宙の姿なのではないか。とすると、真の宇宙の始まりはもっと前にあったはずだ・・・。
答は次項にある。
*
これはエネルギー密度が小さくなれば温度が下がるということでもある。それを知るには、断熱された空間中に高圧のガスを噴射すればよい。断熱空間中の温度はみるみる降下する。ガスは高圧下では高いエネルギー密度をもっていたが、断熱空間中では一気に膨張してエネルギー密度が減少するために温度が下がるのである。断熱膨張という名で知られており、冷凍システムなどに応用されている。
4.宇宙の始まりの二大仮説
宇宙の本当の「始まり」とは何か、という問いに対する有力な解答としては次の二つがある。
1.宇宙は「トンネル」から出現した
ビレンキンという学者が唱えた。「無」に量子的な“ゆらぎ”が生じ、ここからトンネル効果*1によって宇宙が出現したとする。
2.宇宙は「虚数時間の量子宇宙」をへて「実時間宇宙」に転移した
車椅子の天才、ホーキングが唱えた説で、境界なき境界理論という。ビレンキンのいうトンネルとは虚数時間をもつ量子宇宙であるとし、その量子宇宙が“極限の小ささ”まで膨張しきった先が実時間宇宙で、それがすなわち宇宙の出現であるとした。
宇宙が「トンネル」から出現したにせよ、「虚数時間の量子宇宙」から転移したにせよ、出現したての宇宙のサイズは極限の小ささ(10-33cm*2)であった。質量のない粒子だけがエネルギーのみをもって光速で飛び交い、その輻射エネルギーによって宇宙は超高温(絶対温度1032度*3)状態となっていた。また、その輻射エネルギーは重力を生み出していた。重力は質量の存在によって生ずるが、相対性理論のE=mc2によって質量とエネルギーとは等価なので、エネルギーが存在すれば重力も生ずるのである*4。したがってこの宇宙には、輻射エネルギーとともに重力エネルギーも存在していた。
こうして自然界の四つの力*5のうち重力だけは分化していたが、他の三つの力はまだ一つにまとまっていた。
ところで、物質のまだ存在しないこの宇宙空間を占める真空は、現在の宇宙空間を占める真空にはほとんど存在しない(そうでもないという説もある)真空のエネルギーというものをもっていた。これは原始の真空を水、現在の真空を氷にたとえるとわかりやすい。水のほうが氷よりもエネルギーのレベルが高いのは自明であろう。ただし、この頃の宇宙全体に占めるエネルギーの割合は輻射のエネルギーのほうが優勢であった。しかし、宇宙が自然膨張して輻射のエネルギーが弱まるにしたがい*6、相対的に真空のエネルギーは強まっていった。真空のエネルギー密度はその性質上、空間の膨張によらず一定のままだからだ。また、この真空のエネルギーには重力とは逆向きの斥力が働いていた。この斥力は、アインシュタインが捨て去ったあの宇宙項(本章の1参照)がもたらす斥力に相当するものである。これから、真空のエネルギーというのは宇宙項に相当するものであることがわかる。
出現したての宇宙は結局のところ、輻射のエネルギーがおよぼす重力と、真空のエネルギーが及ぼす斥力とが拮抗して慣性的な自然膨張をしていたと思われる。ところが、宇宙が出現して10-36秒が経過したとき、この宇宙はいきなり急膨張する。インフレーションと呼ばれるこの現象については、本章の7で詳しくお話しすることにしよう。
*1 素粒子のような極微世界では、粒子は波としての性質ももつ。このために障壁があっても、あたかもトンネルを通るがごとく、粒子はその障壁を波として通り抜けることができる。
*2 現在の物理学で考えられている最小のサイズ。プランク長さという。
*3 現在の物理学で考えられている最大の温度。プランク温度という。この温度は、前項で述べたように、現在の宇宙を収縮させていったときの温度上昇を計算することで得られたものである。無からの宇宙創成後10-44秒(プランク時間)にまでさかのぼるとこの値になる。このプランク時間より前は、量子論的なゆらぎのために物理的な時間とか空間の概念が通用しなくなる。
*4 これはむしろ、重力は質量ではなくエネルギーに対して働くというのが本質的には正しい(質量とはエネルギーの仮の姿といってもいいかもしれない)。輻射エネルギーの代表格は光エネルギーであるが、この質量をもたない光にも重力は働くのである。
*5 重力、電磁力、弱い力、強い力の4つ。弱い力とは放射性元素を崩壊させる力、強い力とは二つ以上のクォークを一つの陽子や中性子にまとめ、さらには陽子や中性子を原子核にまでまとめる力である。
*6 輻射という現象も、量子論的には波として伝わっていく空間のひずみと考えることができる。よって、空間が膨らめば輻射の波長も伸びてエネルギーは弱まり温度も下がる。
5.「始まり」を特定する必要のないホーキング宇宙とは?
車椅子の天才、ホーキングの業績はほぼ三つに集約できる。「特異点定理の証明」と「ブラックホール蒸発の理論」、そしてちょっとキワモノっぽい「境界なき境界理論」だ。ブラックホール蒸発の理論は本章の16で解説するので、ここでは残りの二つについてお話しよう。
特異点定理の証明というのは、よき親友であり、よきライバルでもあるロジャー・ペンローズとの共同研究の産物である。アインシュタインの一般相対性理論にしたがうかぎり、宇宙は密度無限大の点から始まらねばならないことを明らかにしたものだ。このような無限大の値をとる点は、あらゆる科学の法則が破綻するために特異点と呼ばれる。
ホーキングはしかし、宇宙の始まりが特異点だなんてことにがまんがならなかったようだ。そこで、一般相対性理論だけでなく量子論をもとり込んだ量子宇宙論を展開し、「宇宙には特異点を特定する必要はない」ことを証明しようとした。それが境界なき境界理論である。
実は、前項で紹介したビレンキンの「宇宙は無から生まれ、トンネルをくぐって出現した」という説は、宇宙は特異点から出現したのではないということの一つの仮説なのである。特異点を「トンネル」に置き換えたわけだ。これに対して、ホーキングの境界なき境界理論では、そのトンネルとは虚数時間をもつ量子宇宙であるとし*1、その量子宇宙は「いつ、どこで」を特定する必要のない始まりで生じたとする。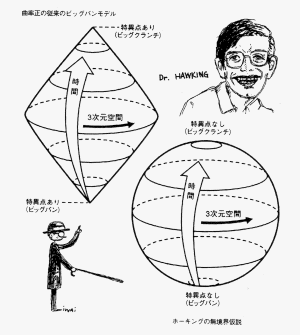
ところで、先述の特異点定理の証明(宇宙は特異点から始まらねばならなかったとする説)というのは、現在の宇宙論の標準宇宙モデルである「フリードマン宇宙」に沿って展開されたものだ。ロシアの気象学者であるフリードマンの唱えたこのモデルでは、空間の運動は宇宙に存在する物質密度によって決まるとする。現在の宇宙が膨張しているというのも、このフリードマン宇宙モデルから導かれるものであり、それはハッブルの観測によって確かめられている(本章の1参照)。
一方、特異点を否定すべくビレンキンとホーキングがとりあげた宇宙モデルというのは、オランダの天文学者であるド・ジッターが提案した「ド・ジッター宇宙」と呼ばれるものである。ド・ジッター宇宙は宇宙項に重きをおいた宇宙モデルだ。宇宙項というのは、アインシュタインが宇宙を静止させようとして宇宙方程式につけ加えたもので*2、物質の影響を受けないポテンシャルエネルギーという性質をもち、空間に斥力(重力とは反対向きの力)をもたらす。
ド・ジッターは、宇宙に物質の占める割合はきわめてわずかである(つまり物質の影響は考えない)とすると、宇宙は無限の過去から収縮してきて、ある極限の小ささになると宇宙項の斥力によって跳ね返り、急激に膨張することを示した。この“極限の小ささの宇宙”に対して、ビレンキンによればそれが無の状態をもとりうるとして、その無からトンネル効果によって宇宙が出現したということになるし、ホーキングによればそれは虚数時間の量子宇宙であり、その量子宇宙が境界なき境界をしみ出て実時間宇宙に転移したことになる。
さて、ホーキングのいう量子宇宙の宇宙空間を、地球の緯線の広がりにたとえてみるとこうなる。
量子宇宙は北極で始まり、時間とともに四方に広がっていき、赤道で最大となり、そのあと広がりは小さくなっていって、南極でゼロに縮んでしまうが、北極(始まり)も南極(終わり)も、物理的には何らほかの点、たとえば東京やニューヨークと異なることのない球面上の一点であって、決して特別な点ではない。つまり、物理的にありえない点(すなわち特異点を)特定する必要がないということだ。境界なき境界理論といわれるゆえんである。
*1
時空の区別のつかない量子世界に虚数の時間を与えると、一般相対性理論の時空で成立する時空の定理がそのまま量子世界でも成立する。つまり、量子世界の時空と一般相対性理論の時空とがつながる。
*2
宇宙項を導入したアインシュタインの宇宙方程式では、曲率(本章の8参照)が正の場合、時間的に変化しない静止した宇宙の解が得られる。
※図は「POPな宇宙論」(佐藤勝彦監修、同文書院刊)より引用
6.時間は逆流するか?
ホーキングのいう量子宇宙を地球になぞらえた話を前項でした。本項はそのつづきである。
量子宇宙は、赤道で最大(極限の小ささ=プランク長さ)となるが、その後さらに膨張しつづけるか、収縮に転ずるのかは微妙なところである。膨張しつづければ実時間宇宙となるし、収縮に転じれば南極でゼロに縮んでしまう。
この量子宇宙の地球型モデルを、量子だの虚数時間だの実時間だのといわず、唯一あるがままの宇宙本来の姿であるとするとどうなるのか。超ミクロな量子宇宙の描像を、超マクロに拡大するわけである。
この宇宙の空間軸は「緯線」、時間軸は「経線」である。宇宙空間の膨張と収縮は緯線の広がりの変化である。北極においてはその広がりはゼロ、赤道で最大となって縮小に転じ、南極では再びゼロになる。空間と時間とは一体のものであるから、空間のない北極と南極では時間もゼロとしよう。つまり、経線(時間軸)を極に向かえば時間はゼロに近づいていてゆく。
このような時空で、北極から膨張していく宇宙は、膨張するにつれ時間がたってゆく。ところが、赤道で(南極へ向けて)縮小に転じるや、時間は何とゼロに向かってゆく。つまり、時間が減少していく。
これは時間が逆流するということである。そこでは、人は記憶をいっぱいにした状態から徐々に記憶を失っていく。あるいは、生き物は死からよみがえり、若返ってゆき、やがて赤ん坊となって誕生を迎える。この空間の収縮と時間の逆流を宇宙の次なる膨張への助走と考えると、宇宙が縮んで南極でゼロになった瞬間、宇宙は赤道へ向かって膨張に転ずる。宇宙は輪廻転生するのである。
ホーキングは一時、これと似たようなことを大真面目に唱えたことがある。まさにSFの世界だ。しかしその後、時間に対する認識の部分でホーキングの考えに矛盾があることが指摘され、ホーキングは結局、時間は一方向にしか流れないことを認めて、あわてて自説をひっこめてしまった。どこか憎めないホーキング先生ではある*。
*
進行性筋萎縮症にあるにも関わらず、彼はユーモアを忘れない。いわく「脳が筋肉でできていなかったのは、不幸中の幸いだった」
7.ただ飯理論といわれるインフレーション宇宙の秘密
宇宙が「トンネル」から出現したにせよ、「虚数時間の量子宇宙」から転移したにせよ、この誕生したての宇宙は10-36秒が経過するといきなり急膨張する。この宇宙の急膨張は、ド・ジッター宇宙モデルが要請するところでもある(本章の5参照)。
この宇宙の急膨張は、真空の相転移の前触れとしての“過冷却”によってもたらされたという。相転移というのは、水が氷(あるいは水蒸気)に変わるような現象をいう。それと同じようなことが原始の真空でも起こり、水にたとえられる原始の真空が、氷にたとえられる真空へと相転移し、現在にいたっているという。
水も氷も、おのおの内部エネルギーというものをもっている。水そして氷にたとえられる原始の真空にもそれに相当するものがあり(といっても量子的なポテンシャルエネルギーだが)、それを真空のエネルギーと呼ぶ。
水と氷の場合、「水」がより内部エネルギーの低い「氷」に相転移するときには、両状態のエネルギーの差は熱として放出されるが、「氷」が「水」に相転移するときにはその分の熱を周囲から吸収する。このときに放出されたり、吸収されたりする熱のことを潜熱という。
以上を原始の真空の場合に置き換えてみると、水に相当する原始の真空が自然膨張するにつれて冷えて、氷に相当する真空に相転移した際には、両者の真空のエネルギーの差は熱として放出されたはずである。このときの真空のエネルギーの差を、真空のエネルギーギャップと呼ぶことにする。
さて、水の場合は通常、0度で相転移(凝固)し始めるが、条件がよいと0度以下になっても相転移しないことがある。これを過冷却という。本来ならば潜熱として放出されるべきエネルギーが放出されず、不安定な状態でエネルギーを抱えこんだかたちとなる。水の温度がさらに下がると相転移は自ずと始まるが、潜熱はこのときに一気に放出される。このときに放出される熱の大きさは過冷却が起こらなかった場合よりもずっと大きく、これがために水の温度は急上昇し、0度(あるいはそれ以上)に達したところでやっと安定な状態となり、その後徐々に水の温度は下がっていく。
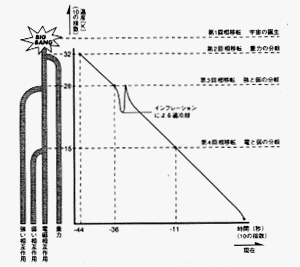
原始の真空でもこの過冷却が起こったという。そのため、潜熱として放出されるべきエネルギーを不安定に抱えこんだ高エネルギーレベルの状態となる。このため、それまでは真空のエネルギーと拮抗していた輻射のエネルギーは劣勢におちいって真空のエネルギーのほうが強大となり、真空のエネルギーによる斥力が輻射のエネルギーによる重力に打ち勝って真空(空間)はいきなり膨張する。空間が膨張すれば輻射のエネルギーによる重力は小さくなるから*1、真空のエネルギーによる斥力の優勢はそのまま変わることなく、真空はどんどん膨張していく。
本章の4でも述べたように、真空のエネルギー密度というのはその膨張によらず一定のままであるから、このときの真空はそのエネルギー密度を一定に保ったまま急膨張を遂げたことになる。これは宇宙のエネルギー総量が急激に増えつづけていったことを意味する。エネルギーは増えも減りもしないというエネルギー保存則からすると、これは明らかにおかしいのではなかろうか?
ここで“現在”の宇宙空間における力学の法則について考えてみよう。それによれば、2つ(べつにいくつでもいいのだが)の物体があるとき、それらの間には引力(重力)が働いており、その引力に逆らって二つの物体を互いに引き離す(卑近な例では物を持ち上げる)のには仕事が要る。この仕事は重力エネルギー(ポテンシャルエネルギー)として蓄えられる。これは、物体どうしが互いに離れたところにあるという状態の内には、重力エネルギーというものが秘められていることを意味する。この互いに離れた物体どうしは、解放されると加速しながら互いに近づくが、このとき引力はどんどん大きくなりつつ重力エネルギーは物体の運動エネルギーへと転化されていく。
では、斥力によってどんどん膨らみつづける宇宙空間にこの両物体があったとしたらどうなるであろう。この宇宙空間における力学のベクトルは現在の宇宙空間における力学のベクトルとはまったく正反対の向きをもつから、両物体は斥力の作用によって互いに離れていくだろう。現在の宇宙空間の場合は二つの物体は引力によって互いに近づくのが自然なのだが、この宇宙空間にあっては斥力によって互いに離れるのが自然なのである。したがってこの宇宙空間においては、斥力に逆らって二つの物体を互いに引き寄せるのに仕事が必要となる。この仕事も重力エネルギーとして蓄えられる(現在の宇宙の場合とは向きが逆のエネルギー)。これは、物体どうしが互いに近いところにあるという状態の内に重力エネルギーが秘められていることを意味する。この互いに近い物体どうしが解放されると両物体は加速しながら互いに離れるが、このとき斥力はどんどん大きくなりつつ、重力エネルギーは物体の運動エネルギーへと転化されていく。
以上のように、原始の膨張宇宙での力学においては、物体どうしが互いに近いところにあるという状態の内に重力エネルギーが秘められているということになるのだが、原始の宇宙には物質はまだ存在していないのだから、上述のことはこう言いかえることができる。すなわち“宇宙がより小さい(距離が短い)状態の内に重力エネルギーが秘められている”と。そして宇宙が膨張して距離が広がるにしたがいその重力エネルギーは運動エネルギーに代わる“あるエネルギー”へと転化されていったと。
その“あるエネルギー”とは真空のエネルギーである。なぜなら、互いに離れていく物体の運動エネルギーとは空間を膨張させるエネルギー、すなわち真空のエネルギーと等価なものだからだ。原始の真空がいくら膨張していっても、真空のエネルギーは重力エネルギーによって次々とまかなわれていくわけだから、真空のエネルギー密度はつねに一定に保たれる。
これが原始の真空の急膨張に秘められたカラクリである。過冷却によるきっかけがあっただけで、原始の真空はそのエネルギー密度を一定に保ったまま急膨張を遂げたのである。これは真空のエネルギー総量が急激に増大したことを意味する。原始の真空は重力エネルギーを代償として莫大なエネルギーを手に入れたわけである。この理論が別名「フリーランチ(ただ飯)理論」といわれるゆえんだ。ただし、どんなに莫大ではあっても、増大した分の真空のエネルギーというのは真空の急膨張によって解放される重力エネルギーの転化されたものであるから、エネルギーの収支は差し引きゼロである。
こうして原始の宇宙は急膨張を遂げたわけだが、その膨張の様子はとほうもなくすさまじいものであった。野球のボールが、直径一兆光年というとんでもない大きさにまで膨らむほどのものすごさだったのだ。しかも、宇宙出現後10-36秒から10-34秒までの間にそれをなしとげた。光速なんかものの数ではない膨張速度だ*2。宇宙はこの急膨張によって一cmほどの大きさになったという。あまりにもすごい急膨張で、しかも一見理不尽にも思える現象なのでインフレーションと名づけられた。
インフレーションの因となった過冷却が終焉すると真空の相転移が始まる。この相転移のときに真空のエネルギーギャップは熱(潜熱)として放出され、宇宙は過冷却によって急降下した温度を一気にとり戻す。宇宙は真空のエネルギーに代わる膨大な熱エネルギーを手中にするわけである。ガモフの唱えたビッグバンとは、この宇宙の再加熱の時点のことであり、このあとの宇宙の描像に対しては、現在の宇宙論の標準宇宙モデルであるフリードマン宇宙が適用される。
インフレーションのあともこの宇宙は膨張しているが、それはインフレーションの急膨張の後に残された勢いによって膨らんでいるのだ。この勢いの速度と宇宙の重力とのからみで宇宙の将来が決まるという(本章の11参照)。
考えてみれば、アインシュタインは、宇宙を静止させようとして宇宙項を導入した。ところが、その宇宙項(すなわち真空のエネルギー)こそがインフレーションの原動力となった。宇宙を静止させるどころか、この世で考えうる極限規模の急激な空間変化の源となったのである。宇宙はやはり静止することはないのだ。そしてもし、原始の宇宙にインフレーションが起こらなかったなら、宇宙はその出現後一秒もしないうちに収縮に向かっただろうという。つまり、インフレーションの起こらない宇宙の寿命はたったの1秒なのである。しかし、インフレーションが起こったために、宇宙の寿命はいっきに引き伸ばされ、一五〇億年後の今日も宇宙は膨張しつづけているのだ。
最後となってしまったが、インフレーション説を提唱したのは日米の二人の宇宙物理学者である。佐藤勝彦とアラン・グースがほぼ同時期(1980年)に、それぞれ独立に唱えた。
*1 この輻射という現象も、量子論的には波として伝わっていく空間のひずみと考えることができる。よって、空間が膨らめば輻射の波長も伸びてエネルギーは弱まり、重力も弱まる。
*2 光速より速い物理現象があるのはおかしいと思われるかもしれないが、これば別に相対性理論とは矛盾しない。相対性理論で禁止されているのは、ある出来事の情報が光速以上で他の場所に伝わって何らかの影響を及ぼすというようなことで、このようなことはありえないことを「相対論的な因果律」という。この原則が破れると相対性理論では時間を逆行できることが示され、結果が原因の前にくるという、まったくおかしなことになる。現在の物理学では、基礎原則として因果律は破られてはならないこととされている。しかし、もし、光速以上のスピードをもつ物体があっても、その物体が光速以下の物体となんの相互作用もしないのであれば、この物体は相対論的因果律に矛盾せずに存在しうる。(松原 隆彦氏の個人サイト中の「宇宙論よくある質問」より引用)
※2点の図のうち上の図はNASDAホームページ「オンラインスペースノート」(http://spaceboy.nasda.go.jp/Note/Note_j.html)より引用
※下の図は「POPな宇宙論」(佐藤勝彦監修、同文書院刊)より引用
8.宇宙の物質はいかに生み出されたか?
前項で原始の真空の相転移についてお話ししたが、実はこの相転移が宇宙の物質を誕生させたのである。その物質とは、対粒子と呼ばれるものだ。物質とはひと言でいえば質量をもつモノのことだから、対粒子は質量をもっている。
対粒子の存在というのは、たとえば真空中で高エネルギーの光子*1どうしを衝突させると電子と反電子(陽電子)の対が生じることなどから証明されている。非常に大きなエネルギーが与えられると、一見何もないと思える空間(真空)から電子と反電子、陽子と反陽子といった対粒子が発生するのである(対生成)。これは、エネルギーが物質に変わることだといってよい。対粒子はしかし互いに出会うと消滅してしまう(対消滅)。そして、対粒子のもっていた質量は輻射エネルギー*2に変わる。対生成によりエネルギーが質量に変わり、対消滅によりその質量がエネルギーへと戻るわけである。まさに相対性理論でいうところのE=mc2の世界である。
それではなぜ、真空に高エネルギーを与えると対粒子が発生するのだろう。それを正確に説明するには量子論の知識が要るが、量子論は初心者にはきわめて難解である。そこで、正確ではないかわりに、わかりやすいたとえを試みてみよう。
真空にものすごい強力なエネルギーを与えると、真空はそのエネルギーによって己の保持する安定をかく乱されそうになり、ある種のパニックを引き起こしかねまじき状態となる。そのパニックを回避すべく真空は、与えられたエネルギーを物質に変えることによって自身の安定を維持しようとする、と考えてみるのである(まあ、このへんのことになると、ヒッグス粒子がどうとかこうとかの話になって、その粒子は数学的には予言されているところのある「存在」がどうとかこうとかの話になるのだが、そんな高等なことにかかずりあっていると収拾がつかなくなるので、すごく乱暴にこのたとえを用いている)。
さて、原始の真空がインフレーションを起こしている状態というのは、増大する一方の真空のエネルギーをどうにかこうにか抱え込んだ極限の安定状態である。インフレーションが進んで真空のエネルギーが極限的な大きさにまで増大し、これが相転移を引き起こす寸前には、さすがのその真空もパニックにおちいらざるをえない極限状態へと追い込まれる。これを回避すべく真空は、そのありあまるエネルギーを無数の対粒子へと変える・・・。前項で、相転移のときに真空のエネルギーは熱として放出されるといったが、その熱とは、このときに生成される対粒子どうしの衝突によって放出される輻射エネルギーや、対粒子が対消滅して放出される輻射エネルギーなどにより発生したものである。このときの状態が、ジョージ・ガモフ唱えるところのビッグバンに相当する。
宇宙初の物質である対粒子とはX粒子であったとされる*3。X粒子は理論的にその存在が予測されているもので、きわめて重い粒子だという(陽子の質量の1015倍)。
上で対粒子とはX粒子だといっているが、それが対粒子である以上、それの反粒子である反X粒子も当然生み出された。X粒子と反X粒子とは対消滅するから、やがてはこれらの粒子は宇宙から姿を消したと思われる。とすると、現在の宇宙物質はいかにして生み出されたのだろう?
答は、一〇億分の一のずれだという。X粒子が他のX粒子と衝突し、X粒子の大質量にみあった高エネルギーが放出されれば、そこにクォークとレプトン*4が生まれる。反X粒子どうしの衝突の場合なら反クォークと反レプトンだ。そしてクォークと反クォーク、レプトンと反レプトンとは対消滅し、光に変わる。しかし、その対消滅において一〇億個に一個くらいの割合で生き残るクォークとレプトンが存在したという(CP非保存)。
以上をひっくるめていうと、X粒子と反X粒子とはやがては対消滅するのだが、その間に一〇億個に一個くらいの割合でクォークとレプトンとが生きのびるということだ。そして、これらの生き残ったクォークとレプトンが、現在の宇宙に存在するすべての物質の基本構成材料となっていった。現在の宇宙はほとんどカラッポだが、それもわずかにとり残されたクォークとレプトンが宇宙物質の素であったことを考えれば納得がいく。
さて、宇宙誕生から10-5秒後、宇宙の温度は絶対温度一〇兆(1013)度にまで下がっていた。なにしろ誕生時が絶対温度1032度だから、これでもずいぶん冷えたほうなのである。このために、ものすごい勢いで飛び回っていたクォークがついにその勢いを弱め、核力(強い力)によってつながれて陽子や中性子となった。しかし、温度がまだ十分に下がっていないために、できてはすぐに崩壊するということを繰り返していた。
宇宙誕生から一秒後、温度は絶対温度一〇〇億度にまで下がった。陽子と中性子とははっきりと固定され、核力によってくっつき合って原子核を形成し始めた。三分後、もっとも簡単な構造の水素とヘリウムの原子核が完成するが、宇宙の冷却速度が速かったために、それよりも重い元素の原子核はとうとう形成されなかった。核の形成にもそれなりの熱エネルギーが必要なのである。一方、マイナスの電気をもつ電子(レプトンの一つ)は、陽子のもつプラス電気を振りきって宇宙を自由に飛びかっていた。このため、宇宙にあふれる光は電子のバリアに進路を妨害され(当時の宇宙は手のひらに載るほどの大きさでしかなかったことに注意)、直進できない状態にあった。
そしていっきに三〇万年後(一〇万年後とする説もある)になると、宇宙の温度は絶対温度三〇〇〇〜四〇〇〇度くらいにまで下がっていた。電子の熱運動は極端に弱まって陽子のプラス電気にとらえられ、原子核のまわりを回るようになった。記念すべき原子の誕生だ。水素七、ヘリウム三の割合で宇宙に初めて元素が形成されたのである。
*1
本章の2で、光とは、量子論的な観点からは波として伝わっていく空間のひずみであるといった。また量子論的には、光は粒子という性質をも併せもつ。この粒子としての性質に注目した場合の光を光子と呼ぶ。
*2
輻射エネルギーとは、質量をもたない粒子がもつ仮想的ではあるが実体をともなう運動エネルギーのことであり、波としてみたときの波動エネルギーでもある。質量をもたない粒子の例としては光子があげられる。
*3
クォークとレプトンが合体したレプトクォークだとする説もある。もちろんこれも理論上の粒子である。
*4
すべての物質は物質粒子であるクォークとレプトンからできている。クォークは、原子核を構成するハドロンと呼ばれる粒子(陽子、中性子、中間子など)を形づくる基本粒子で、強い力に感じる。また「色」という性質ももっている。クォークは六種類あると考えられており、軽いものから順に、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップと呼ばれている。単体では存在しない。またレプトンは強い力に感じない粒子で、電荷をもつ粒子である電子、ミュー粒子およびタウ粒子と、それらの各々に対応する中性のニュートリノとの計六種類がある。
9.銀河と星の誕生ドラマ
宇宙最初の元素である水素とヘリウムが形成されていくにしたがい(前項参照)、宇宙を自由に飛び交っていた電子は次々に元素に吸収されて消えうせていった。このため、それまで電子に進路をじゃまされていた光はやっと直進できるようになり、宇宙はすっきりと見通せるようなった。これを“宇宙の晴れ上がり”という。本章の2で紹介した宇宙背景放射とは、このときの光のなごりなのである。
さて、この時期の宇宙というのは、それまでの光ばかりの時代から、物質の時代へと移り変わっていく頃合でもある。それまでは、真空の相転移によって誕生した宇宙最初の物質である対粒子の対消滅などによって放出されていた光(輻射エネルギー)が宇宙を支配していたのだが、宇宙の膨張にともなって光の波長が伸び、エネルギーを失っていったために、相対的にわずかにとり残されたクォークとレプトンによって生み出された物質群のほうが優勢になったのである。そして重力源の主役も、輻射エネルギー(光)から物質へと移った。
宇宙が晴れ上がって、光が電子や原子核に激しくぶつかるときの圧力が小さくなると、それまでその圧力にじゃまされていた物質の重力(引力)のほうが優勢となり、重力の大きなところ(物質密度の高いところ)には周辺の物質が吸引されて大きな塊が形成された。銀河の誕生である。
誕生したばかりの銀河は、軽い水素とヘリウムからなるガスのみでできていた。このガスの広がりのある部分に、何かのはずみで密度の濃い部分が生じた。その部分のガスは互いの重力で引きつけ合い、初めは非常にゆっくりと、そしてだんだん速く集まり、密度はさらに濃くなっていった。ガスは圧縮されるにつれ熱くなり、やがて中心部の温度は絶対温度一〇〇〇万度にも達した。この高温によって水素は核融合反応を起こし、強く輝き始め、ついに星となった*1。
散りぢりであったガスが集まり始めて、それが星となるまでには、一〇〇〇万年から一億年くらいの長大な時間を必要とする。こうした星を主系列星といい、現在確認されている星の九〇%以上がこの主系列星に属する。その質量は太陽質量の一〇分の一から三〇倍だ。
さて、こうしてできあがった宇宙というものを、私たちはいま見ているわけだが、この宇宙には、まだ解決されねばならない重要な問題が残っている。それは、この宇宙が平坦なのかどうか、一様であるのかどうかということだ。
宇宙が平坦であるとは、宇宙が曲率*2ゼロで膨張しつづけることをいう。アインシュタインの宇宙方程式によれば、宇宙は膨張から収縮に転ずるか(正の曲率をもつ閉じた宇宙の場合)、負の曲率で膨張しつづけるか(開いた宇宙の場合)、曲率ゼロで膨張しつづけるか(平坦な宇宙の場合)のいずれかなのだ。また、宇宙が一様であるとは、宇宙の物質密度がほぼ均一であるということだ。
九〇年代に入る前までは、宇宙は平坦で一様であるとみられていた。それに対するインフレーション説の説明はこうであった。
宇宙の創成*3とインフレーションの間のゆるやかな膨張のとき、宇宙には“存在が一様にゆき渡る”ゆとりがあった。その世界はインフレーションによる急膨張へと一気に転ずるが、一様性はそのまま残った。また、宇宙創成の直後には空間に歪みがあったはずだが、それもすさまじい急膨張によってビョーンと伸ばされてしまい、丸い大地が私たちの目には平面と見えるように、ほとんど平坦に見えるようになった・・・。
ところが、九〇年代に入ると宇宙の大規模構造などが見つかり、宇宙はどうやら一様ではないという見方が出てきた。しかし、それに対してもインフレーション説はつじつまの合う説明を用意するのである(本章の12参照)。何とも重宝な理論ではある。
*1
宇宙初期の天体としては、これまでクェーサー(準星)が知られていたが、最近では、宇宙誕生後一〇億年に形成されたとみられる原始銀河も発見されている。
*2
曲率とは空間の歪みを表わす尺度。交わらない直線が無数に存在しうるのが負の曲率をもつ世界(馬の鞍の表面)であり、そういう直線が存在しない世界が正の曲率をもつ世界(球面)、そしてそのような直線が一本のみ存在するのが曲率ゼロの世界(平面)である。
*3
本書では、宇宙の“創成”というときは、ビレンキンやホーキングが唱えた究極の宇宙誕生をさし、宇宙の“開闢”というときは、ジョージ・ガモフの唱えたビッグバンをさすものとする。
10.星の「死」が生命を「誕生」させた
宇宙物質のたった三%を占めるにすぎないとされる重い元素(水素とヘリウム以外の元素)は、実は星(主系列星)の死によって生み出された。これらの重い元素は、生命の誕生に欠かすことのできない物質だ。まさに、星の「死」が生命を「誕生」させたというわけだ。
星の死の原因は、中心部の水素の核融合反応の停止である。これによって重力収縮が始まるるが、そのときの超高圧によって中心部の水素に核融合が再発する。が、太陽よりも軽い星の場合は重力収縮が十分ではなく、水素に核融合が再発しないこともある。こうした星は、少しずつ収縮しながら赤外線を放出していき、数十億年かかって冷えていく。褐色矮星と呼ばれているが、観測にはまだひっかかっていないようである。ダークマター(次項参照)の候補にもあげられている。
太陽と同等の質量の星は、核融合によって水素を使い果たすと赤色巨星となり、次いで白色矮星となり、しまいには冷えきって見えなくなる(第3章の1参照)。
また、太陽の八倍くらいまでの質量の星では、赤色巨星になっても、その芯の周囲でなされるヘリウムの核融合エネルギーによって重い元素の原子核が形成され、酸素や炭素などが生み出される。これの量がどんどん増えていくとやがてものすごい勢いで燃え始め、ついには星全体が噴き飛ぶにいたる。これにより、酸素や炭素が宇宙にばらまかれる。
問題は、太陽よりも八倍以上重い星の場合である。こうした星では、中心部で再発した水素の核融合反応がさらに先へ進み、水素やヘリウムはもとより、炭素、ネオン、酸素、珪素、コバルト、ニッケル、さらには鉄までも形成される。重い元素ほど中心部に片寄るから、ここに並べた物質の順序は、この星の外郭から中心部までを形成する物質の順序でもある。すなわち、いちばん外側が水素とヘリウム、中心部が鉄である。
この星は、その最期には赤色超巨星にまで膨れ上がる。ところが、その質量があまりにもすごいために、最終的には自分の重みを支えきれずに収縮する。このときの圧力は桁違いに大きなもので、星の芯では鉄原子そのものが破壊され、この世でもっとも硬い中性子だけになってしまう。そして、この中性子だけの芯に向かって周囲の物質が秒速何千kmというものすごいスピードでぶつかっていく。その激しい衝突はすさまじい衝撃波を生み、この衝撃波によって星は大爆発する。この爆発エネルギーによって核融合がさらに進み、鉄よりも重い元素が形成される。爆発のあとには、半径は一〇kmくらいなのに、質量は太陽ほどもある超高密度な中性子星だけが残る。重い星のこのような最期の大爆発は「超新星」と呼ばれる*。
銀河には、こうした大爆発によって飛散した星の残骸が星間ガスとなって漂う。そして、星の死から生み出された豊富な物質を蓄えた星間ガスからは、再び新たな星が誕生する。太陽もその一つだ。そして、その太陽からは地球が誕生し、その地球には生命が誕生した。生命の源となったさまざまな物質やエネルギーは、すでに死んでしまった星々からのかけがえのない贈り物なのだ。
*
超新星というのは、その爆発の様子に対して名づけられたものである。太陽の一〇〇億倍もの明るさで輝き、一〇〇日ほどで消えてゆくというから、新星の誕生と見えたのであろう。だが、実際には星の最期の有様である。しかし新たなる星を形成する素材ともなるのだから、新星というのもあながち間違いではない。 なお、太陽の三〇倍以上の質量をもつ星は、超新星爆発を起こした後、中性子だけの芯すらもつぶれてブラックホールとなる。
|