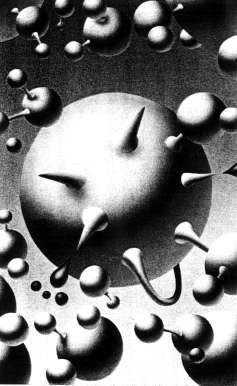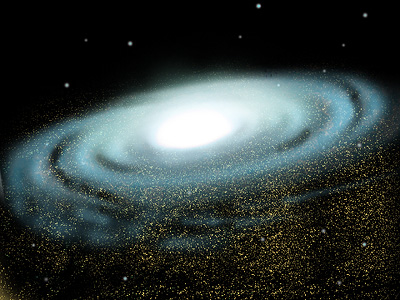|
��Q�́@�F���̓�ɔ���i�Q�j
�P�P�D�����Ȃ������u�_�[�N�}�^�[�v�̐���
�P�Q�D�F���ɂ������̒��邪����I
�P�R�D�F���͖����ɒa�������H�I
�P�S�D�F���̔N��͎��̂Ƃ��뉽�H
�P�T�D�F���́u�N��v���A�F���́u�ʂāv�ł���u�傫���v�ł�������Ăǂ��������ƁH
�P�U�D�u���b�N�z�[���͏�������I
�P�V�D���Ђ����_�́A��ꐢ�I�̐V���������w���H
�P�W�D��͂͂₪�āA�Ђ�����Ǝ���
�P�X�D�������̋�͌n�͂����Ȃ��Ă���
�Q�O�D���̋�͌n�ɂ́A�m�I�����̂̏Z�ސ����������邩�H
�Q�P�D�l�Ԍ����̉F���Ƃ͉�����H
���R������
���E�ō����\�̖]�����u����v���n���C��
�P�P�D�����Ȃ������u�_�[�N�}�^�[�v�̐���
�@ �F���n������C���t���[�V�������ւāA�F�������闎���������x�Ŗc�����Ă���Ƃ����l���悤�B���̂Ƃ��̖c�����x�����F���̑傫���ɂ���Č��܂�ՊE���x�����傫���ƁA�����ȃ��P�b�g���n���̏d�͂��ӂ���Ăǂ��܂ł����ł����悤�ɁA�F�����F���̏d�́i��͊Ԃɓ����d�́j���ӂ���ĉi�v�ɖc�����Â���B����͊J�����F���ł���B
�@���x�����ՊE���x�����������ƁA���x�̑���Ȃ����P�b�g��������n���̏d�͂ɕ����ė�������悤�ɁA�F�����F���̏d�͂ɕ����Ď��k�ɓ]����B����͕����F�����B�����āA���x�����ՊE���x�ɓ�������A���������̑��x�̃��P�b�g���A�₪�Ēn���̏d�͂Ɛ܂荇�������Ēn���̂܂������Â���悤�ɁA�F�����F���̏d�͂Ɛ܂荇���������R�ȏ�Ԃ�ۂB�F���Ƃ����̂͐Î~���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�����ł������R�ȏ�ԂƂ͊����I�Ȏ��R�c���ł���B����͕��R�ȉF�����B�C���t���[�V�������ł́A���̕��R�ȉF����\�����Ă���B
�@���ǁA�c�����x�����ՊE���x�����傫�������������A���邢�͂���ɓ��������ʼnF���̖��������܂�킯���B�ՊE���x�͌v�Z�ɂ���ċ��߂邱�Ƃ��ł���B�����Ă��̗ՊE���x�ɂ͂���ɑΉ�����d�͂̒l�Ƃ������̂����݂��A���̏d�͉͂F���̕������x�ɂ���Č��܂�B���̕������x�̂��Ƃ��u�ՊE���x�v�Ƃ������A��������݂̒l�Ƃ��Čv�Z����ƁA�P��������������P�O-29�O�����ɂȂ�炵���B���ۂ̉F���̕������x������Ɠ�������Ε��R�ȉF���A������傫����ΉF���̏d�͂̂ق��������������߂�͂�����������F���A��������ΊJ�����F���Ƃ������ƂɂȂ�B����͂��Ƃ��F���̕������x����l�ł���Ƃ��Ă̘b���B
�@���ۂ̊ϑ����ʂ��琄�肳���l�́A�P�O-29�O�������͂邩�ɉ����l���Ƃ����B�����M����Ȃ�A�F���͊J���Ă��邱�ƂɂȂ�B�������A�������̉F���͌����ڂɂ͕��R�Ɍ�����B�C���t���[�V���������F���͕��R���Ƃ��Ă���B�Ƃ���A�F���ɂ͂����ƕ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŃN���[�Y�A�b�v����Ă����̂��A�����Ȃ��Í������g�_�[�N�}�^�[�h���B
�@���̕����̑��݂́A�a���̉_�i��R�͂̂P�W�Q�Ɓj�����������ƂŒm����I�����_�̓V���w�҃I�[���g���w�E���Ă����B��͌n�̏d�͂͋�͌n�̍P���ɏ㉺�^���������Ă��邪�A���̏㉺�^�������邩����A��͌n�̏d�͂͌����Ă��鐯�̔{�ȏ���Ȃ��ƌv�Z�ɍ���Ȃ��Ƃ������̂��B�����������Ă���Ƃ������Ƃ���~�b�V���O�E�}�X�Ɩ��Â���ꂽ�B����͈��N�ɒ�N���ꂽ��肾���A���Z�Z�N��ȍ~�ɂȂ�ƁA�_�[�N�}�^�[�̑��݂��w�E����͂������ɑ����n�߂��B
�@�_�[�N�}�^�[�̑����́A�u���b�N�z�[���A�����q���i�O���Q�Ɓj�A���F��A���F��Ȃǂ̌����Ȃ��Â��V�̂�A�j���[�g���m�ł���B�����́A���̑��݂����_�I�ɂ͗\������Ă��邪�����ɂ͌������Ă��Ȃ��������B�A�N�V�I���A���Ώ̐����q�i�t�H�e�B�[�m�A�O���r�e�B�[�m��*�j�A���m�|�[���i���C�P�Ɏq�j�Ȃǂ������ł���B
�@�_�[�N�}�^�[�́A�����Ă��邷�ׂĂ̐��̐��\�{�̎��ʂ����Ɛ��肳��Ă���B
* �t�H�e�B�[�m�̓t�H�g���i���q�j�A�O���r�e�B�[�m�̓O���r�g���i�d�͎q�j�̒��Ώ̐����q�ł���B
�P�Q�D�F���ɂ������̒��邪����I
�@�d�g�]������l�H�q���]�����i�F���]�����j�A�����ăX�[�p�[�R���s���[�^�ȂǁA���݂̉F���ϑ��Z�p�͊i�i�ɐi�����Ă���B���̋��͂ȕ���̂������ŁA�F���̍\���͂��Ȃ薾�炩�ɂȂ��Ă����B
�@����ɂ��ƁA���̉F���͂ǂ����A��ЂƂ̖A�ɐ��炩�琔���̋�͂��܂ނ�������̋�͒c�⒴��͒c������Ȃ��悤�ɓ\������V���{���ʍ\���ɂȂ��Ă���炵���B���̃V���{���ʍ\�����A�t�F���X�̂悤�Ɏl�����N���ƂɋK������������������ł���Ƃ����B���ɂ́A���˂�ǂ̂悤�ɉ��X�ƐL�т���̂��m�F����Ă���A�O���[�g�E�H�[���i�����̒���j�Ɩ��Â����Ă���B�����܉����N�A����܁Z�Z�����N�A�������N�Ƃ����F���ő�̑�K�͍\�����B�V���{���ʂ̌X�̖A�̒��͊��S�ȋŁA�{�C�h�ƌĂ��B�{�C�h�̑傫���͎O�Z�Z�Z���`�ꉭ���N���炢���B
�@������A�F���ɂ͕s���ȏo����������B�������̋�͌n���������͒c�A�����Ă��̋�͒c���܂ޒ���͒c���A������������Ă������X�s�[�h�ň��������Ă���Ƃ����̂��B�͂邩�������N�̔ޕ��ɁA�����ƂĂ��Ȃ�����ȏd�͌�������ł���炵���A���̏d�͂ݏo���Ă��鎿�ʂ́A���z���ʂ̂P�O19�{�Ɛ�������Ă���B
�@���̂悤�ȉF������l�ł���͂��͂Ȃ��B����ɂ��āA�C���t���[�V���������p�ӂ������́A�F���n���̒���A�C���t���[�V�����̑O�ɉF���ɐ������u��炬�v�ł������B���̂�炬���C���t���[�V�����ɂ���Ĉ����L����A�F�������̑n�����ɂ����ĕ������x�ƕ������z�ɉ��ʂ������炵���B�������x�̔Z���Ƃ���́A���ꂪ�^�l�ƂȂ��Ď��Ԃ̗���ƂƂ��ɂ��̃^�l�ɂ�葽���̕������W�܂�A��͂ƂȂ����B�܂��A�������z�̉��ʂ͉F���ɑ�K�͍\���������炵���Ƃ����킯���B
�@���̉F�������n�����̕������x�A�������z�̉��ʂ́A���̐i�s�����܂��������邵�A�����������邩��A�F���̐���オ��i�{�͂̂X�Q�Ɓj�̍ۂɕ��U�������G�l���M�[�̕��z�ɂ��A����Ȃ�̂�炬���������͂��ł���B���������ē����̌��̎c���ł���F���w�i���˂ɂ��A�����̉��x�̂�炬������Ǝv����B�����A�A�����J�̉F���w�i���ˊϑ��q���u�b�n�a�d�i�R�[�r�[�j*�v�́A��Z�����̈�قǂ̉��x�̂�炬���Ƃ炦���B
�@�����b�n�a�d�̊ϑ��f�[�^�͂܂����t�Ȃ��̂ł���A�ʐ^�ł����Ă݂�s���{�P�Ƃ������悤�ȃ��x�����B�����ŁA����Ɋϑ����x�����߂��ϑ��q�����A�C���t���[�V�������̐^�U���m���߂�ׂ��ł��グ����\��ƂȂ��Ă���B
* COsmic Background Explorer�̗��B��㔪�O�N�ɑł��グ��ꂽ���E���̐ԊO���ϑ��q���h�q�`�r�Ɏ����ŁA��㔪��N�ɂm�`�r�`���ł��グ�����E�œ�Ԗڂ̐ԊO���ϑ��q���B���{�̉F���Ȋw���������A��Z�Z��N�ɂh�q�`�r�����̂����\�����h�q�h�r��ł��グ��\��B
�P�R�D�F���͖����ɒa�������H�I
�@�{�͂̂V�ŁA�F���n�����́u�^��̑��]�ځv�̘b�������B���̑��]�ڂ͎��́A�����������ă{�R�{�R�A���悤�ɉF���̎�q�̂��������œ��������I�ɔ��������Ƃ����B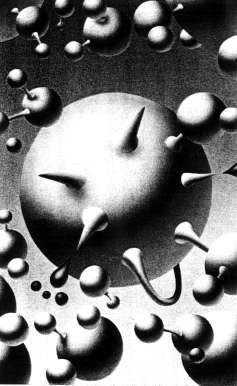
�@���ꂪ�{�����Ƃ���ƁA���ꂼ��̑��]�ڂ͂��ꂼ��̉F�����������͂��ł���B�F���o�����̐^��̃G�l���M�[�ɂ���炬���������Ƃ�������A�Ⴂ�G�l���M�[�̂Ƃ���ł͑��]�ڂ͒x��A�C���t���[�V�������N���炸�A�F���͏��������₩�ɐ������邩�A���k�ɓ]���Ă������ł��낤�B����A�����G�l���M�[�̂Ƃ���ł́A���]�ڂɐ悾���ăC���t���[�V�������N����A�F���͑傫���������Ă������ł��낤�B
�@�������Ăł������ꂼ��̉F���̐^��ł��A��͂�I�A�O���I�ȑ��]�ڂ��N�����Ă���ɐV���ȉF�����������Ƃ�������A���ǁA�e�F�����炢�����̎q�F�������܂�A����ɑ��F���A�Б��F���ƁA�F�������X�Ƀl�Y�~�Z���ɑ����Ă������ƍl������B�������̉F���́A���̒��̂ǂ�Ȃ̂��낤�B
�@�����̉F���̒��ɂ́A�G�l���M�[���\���ł͂Ȃ��A���̂܂ܗ₦�Ă��܂����Â��ȉF����A�C���t���[�V�������r���Ŏ~�܂��Ă��܂��A�Ԃ�Ă��܂����F�������邾�낤�B�܂��A�����̑f�ɂȂ闱�q������o���A�������̉F���Ɠ����悤�ɂȂ����F�������邩������Ȃ��B
�@�����̉F���̒a���͎��Ԃɂ��Ă݂�Ώu���̂��Ƃł���B���������āA�e���q�����A�����Б������������̂ł͂Ȃ��A����疳���ɋ߂��F�����Ђ��߂��������ƂƂȂ�B�������́A�����̉F���̑��݂�m�邱�Ƃ͂ł���̂��낤���H
�@�e�F���Ǝq�F���A�q�F���Ƒ��F���A���F���ƂБ��F���E�E�E�̂��ꂼ��̐e�q�̂Ȃ��蕔���́A�Ђǂ��Ԃ�Ă���ƍl������B�q�F�����e�F������}�����ꂵ�Ėҗ�Ȑ����Ŗc������Ƃ��A���҂̊Ԃ�������ƂԂ�邩�炾�B���̕����̂��Ƃ��A�C���V���^�C���|���[�[���E�u���b�W�Ƃ������A�ŋ߂ł̓��[���z�[���i���H�����j�Ƃ����Ă���B���[���z�[���̒��͂��̂��������x�ɂȂ��Ă���A���̏d�͂͂����܂����A�܂��Ƀu���b�N�z�[���݂����ɂȂ��Ă���B�����鎖�ۂ̒n�����ł���B����ɂ���Đe�F���Ǝq�F���̈��ʊW�͊��S�ɎՒf����Ă��܂��̂ŁA���̂��Ƃ�͂ł��Ȃ��B�܂莄�����́A���̉F���̑��݂�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B
���}�́u�ق̒��̉F���v�i�������F���A���[���j�����p
�P�S�D�F���̔N��͎��̂Ƃ��뉽�H
�@�F���̖c��������Â�����j�I�Ȋϑ����Ȃ��Ƃ����n�b�u���́A���̊ϑ����ʂ��玟�̂悤�Ȗ@�������B
�@�u��͂��������鑬�x���́A��͂܂ł̋������ɔ�Ⴗ��B���Ȃ킿�����g���ł���v
�@������n�b�u���̖@���Ƃ����A�萔�̂g���n�b�u���萔�Ƃ����B�����̋�͂قǁA�������鑬�x���傫���킯�ł���B�Ƃ����Ă��A����͋�͎��g�������Ă���̂ł͂Ȃ��A��͂��Ƃ�܂��F����Ԃ��c�����Ă��錋�ʂȂ̂ł���B�܂��A����Ƃ��납�猩�Ă��܂��܂ȋ����ɂ����͂����́A���ꂼ�ꂪ�قȂ鑬�x�ʼn������邯��ǂ��A���̉������鑬�x�͂˂Ɉ��ł���B�F���̖c�����͂ǂ����˂Ɉ��Ȃ̂ł����Ȃ�̂��B������F���̈�l�Ȗc���Ƃ����B�W���[�W�E�K���t�̏������r�b�O�o���ȍ~�ɉF�������肵���c�����n�߂Ă���́A�F���͈�l�ɖc�����Ă���Ƃ���̂����݂̉F�����_�̗���ł���B
�@�F���c���̈�l������A�u�n�b�u���萔�̋t���͉F���̔N��ł���v�Ƃ����A����������B���̂킯���ȉ��ɐ������悤�B
�@���܁A�_�`����F�����a�����āA�P�b��ɂ��̑傫�����Q�����ɂȂ����Ƃ��悤�B�_�`���猩���F���̉ʂĂ͂Q�����̂Ƃ���ŁA�������������鑬���͖��b�Q�������B�F���̒��ԓ_�͂P�����̂Ƃ���ŁA�����̉������鑬���͖��b�P�����ł���B�_�`���猩�����̂Ƃ��̃n�b�u���萔�i��������_�̑����^���̓_�܂ł̋����j�́A�F���̉ʂĂ��Q�^�Q�A���ԓ_���P�^�P�A���Ȃ킿�Ƃ��ɂP�ł���B
�@�F���̖c���͈�l������A���̂P�b��ɂ́A�_�`���猩���F���̉ʂĂ͂���ɂQ����������������A�F���̒��ԓ_�͂P����������������B���̂Ƃ��̓_�`���猩���n�b�u���萔�́A�F���̉ʂĂ��Q�^�S�A���ԓ_���P�^�Q�A���Ȃ킿�Ƃ��ɂP�^�Q�ł���B���̂P�b��ɂ�����n�b�u���萔�͂P�^�R�ɂȂ邱�Ƃ́A�e�ՂɎ@�������ł��낤�B
�@�F���a������P�b��̃n�b�u���萔�͂P�A�Q�b��̂���͂P�^�Q�A�R�b��̂���͂P�^�R*�B�n�b�u���萔�̋t�����A�F���a���ȗ��̎��ԂƂȂ邱�Ƃ́A����Ŗ����ł���B
�@�n�b�u���萔�́A�����͂̉������鑬���ƁA�����܂ł̋������킩��ΊȒP�ɓ��邱�Ƃ��ł���B���͊ϑ����x�ŁA�n�b�u�����g���ϑ����ē����n�b�u���萔�ɂ��ƂÂ��F���̔N��͓�Z���N�������B���݂ł͂��ꂪ��܁Z���N�ɂ܂ŐL����Ă���B
�@�Ƃ��낪�A�ŋ߂ɂȂ��ĉF���̔N��͑傫����炬�n�߂��B�܂��A�n�b�u���F���]�������ϑ������n�b�u���萔�́A���ݕW���Ƃ���Ă���n�b�u���萔�������Ȃ�傫�������B����̓n�b�u���萔�̋t�����������Ȃ邱�ƁA���Ȃ킿�F���̔N���Ԃ邱�Ƃł���B���Z���`��Z�Z���N���炢�̒l�ɂȂ�Ƃ����B�܂��A�ŐV�Z�p�����ē���ꂽ�n�ォ��̊ϑ��ł��A�n�b�u���萔�͕W�������傫���l�ƂȂ�A�F���N��͈�Z�Z���N�ȉ��Əo���B
�@���̈���ŁA�F���͂����Ƃ���ƍ��N��Ƃ����������Ȃ���Ă���B�O���ŏЉ���F���̑�K�͍\�����ł��オ�邽�߂ɂ́A���Ȃ��Ƃ��Z�Z�Z���N�͂�����Ƃ����̂��B�F���̔N��͂܂�����A���ׂɂ��������Ă��܂����B
* �n�b�u���萔�͂��̂悤�ɁA���ԂƂƂ��ɕς��l������A�{���͒萔�Ƃ͂����Ȃ��B�������A�l�Ԃ����ɂ��鎞�ԓ��ł̉F���̖c���Ȃǃ[���ɓ���������A�萔�Ƃ��Ĉ����Ă����������Ȃ��̂ł���B
�P�T�D�F���́u�N��v���A�F���́u�ʂāv�ł���u�傫���v�ł�������āA�ǂ��������ƁH
�@�n�b�u���̖@���ɂ��A�����ɂ����͂قǍ����ʼn�������B�\���ɉ����ɂ����͂́A���ɂ͂��̐��̍ō����x�ł�������ʼn�������ł��낤�B�����Ă����艓���Ƃ��납��͌����I�Ɍ��͓͂��Ȃ��B����Ȃ����E�́u�����Ă��Ȃ����E�v�ł���A�������̐��E�̂��Ƃ͂킩��悤���Ȃ��B���������āA�����ʼn��������͂������ĉF���̉ʂĂƂ���ق��͂Ȃ��ł��낤�B�܂�A�������u�F���̒n�����v�ł���B
�@���āA�F���̑傫���Ƃ͉��ł��낤�B����������Ƃ��납��F���̉ʂāi�����ʼn��������́j�܂ł̋����ł��낤���B����Ƃ��A�J蓎��ȗ����݂܂Ŗc��݂Â��Ă����F���̖c�������ł��낤���B����͎��͂ǂ�����������̂ł���B���ꂪ�ǂ����ĂȂ̂��A���ꂩ�炨�b���悤�B
�@���܁A�����ʼn��������͂��ϑ����Ă���Ƃ���B���̋�͂܂ł̋��� �q �̓n�b�u���̖@������ �q�����^�g �ł���i�O���Q�Ɓj�B�܂��A�n�b�u���萔�̋t���ł��� �P�^�g �͑O���ł��������悤�ɉF���N��ł��邩��A����� �s �Ƃ����Ǝ��� �q��c�s �ƂȂ�B
�@���̎��͂���Ӗ��Ŋ�Ȏ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̋�͉͂F���N��� �s �������Ď���̌������݂ɓ͂��Ă���Ƃ����߂ł��邩��ł���B�F���N��Ԃ������̂ڂ��Ċϑ�������͂̎p�Ƃ������Ƃł��邩��A���̋�͂͂܂��ɉF���J蓎��̋�͂ł���B
�@�����̂��Ƃ���A�q �Ƃ����͉̂F���̉ʂĂ܂ł̋����ł���A���A�F���J蓎��̋�͂��甭����ꂽ�����A�F���N��Ԃ������Ėc������F����Ԃ�`����Č��݂ɓ��B����܂łɂ��ǂ��Ă��������Ƃ������Ƃł�����B���ꂪ�A�O�q�̖₢�ɑ��铚���ł���B
�@�F���ɂ����鋗���͒ʏ�u���N�v�ŕ\�킳���B�F���̑傫�������N�ŕ\�킷�ɂ́A�q �̒l��������N�ɐi�ދ����Ŋ���悢�B������N�ɐi�ދ����͈�N�� �� �b�Ƃ���� ���� �ł���B�u�q�����s�v�ł��邩��A���s �� ���� �Ŋ��������̂��A���N�ŕ\���ꂽ�F���̑傫�����B���̒l�� �s�^�� �ƂȂ�B�s�^�� ���N�Ƃ������Ƃ��B
�@�s�^�� �Ƃ����̂́A�F���N�� �s ����N�Ԃ̕b�� �� �Ŋ��������̂ł��邩��A�N�P�ʂŕ\�킳�ꂽ�F���N��ł���B����͌��݈�܁Z���N�Ƃ���Ă��邩��A�F���̑傫���͈�܁Z�����N�ƂȂ�B�܂�A�N�P�ʂƂ��ĕ\�킳�ꂽ�F���N��i�n�b�u���萔�̋t���j�Ɂu���N�v����������������ΉF���̑傫���i�F���̉ʂĂ܂ł̋����j�ƂȂ�B�n�b�u���萔�������ɏd�v�ȈӖ��������������A����ł킩�邾�낤�B
�P�U�D�u���b�N�z�[���͏�������I
�@�u���b�N�z�[���̑��݂����߂ė\�������̂́A�ꔪ���I���̓V�ː��w�ҁA���v���X���B�ނ̂����u���b�N�z�[���Ƃ́A������ƖѐF�̕ς�������̂ł���B���Ƃ��Βn�������[��Ƒ傫�����Ă����ƁA�n������̒E�o���x�͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ�A���ɂ͌����ȏ�ɂȂ�B�����Ȃ�ƌ�������n��Ɂg�����h���Ă��܂��B���͒n������o���Ȃ�����A���̐�����͒n���ɂ��ĉ����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂�A�n���̓u���b�N�z�[���Ɖ����̂ł���B
�@���݂ł����u���b�N�z�[���Ƃ́A�d�������R���������Əd�͂ɂ���Ăǂ�ǂ���k���Ă����A���ɂ͌������������Ă��܂��Ƃ������E���B�����o�Ă��Ȃ��̂ŁA�������ǂ��Ȃ��Ă���̂��킩��悤���Ȃ��B�����ŁA�u���b�N�z�[���̓�����̂��Ƃ��u���ۂ̒n�����v�ƌĂԁB���̒n�����̌��������ɂ͕����I�ɂ͉������݂��Ȃ��B�����������A�����_�ɋz�����܂�Ă��܂����炾�B���̓_���̂��āu���ٓ_�v�Ƃ����B
�@�u���b�N�z�[���ɂ͊m���ɕ����I�ɂ͉������݂��Ȃ����A����ȕ������̂ݍ����ٓ_�ɂ͖�����̎��ʂ�����A�u���b�N�z�[���ɂ͂��̎��ʂɂ�邷���܂����d�͂����݂���B
�@���́A���������̂ݍ���ł��܂��u���b�N�z�[������������Ƃ����B�Ԉ֎q�̓V�ˁA���̃z�[�L���O���������B
�@�ނɂ��ƁA�u���b�N�z�[���̋ߖT�̋�Ԃł��ʎq�I�Ȃ�炬�͐����邽�߁A���q�Ɣ����q����Ȃ�Η��q�i�{�͂̂W�Q�Ɓj��������Ƃ����B�����āA�Ώ��ł���O�ɔ����q���u���b�N�z�[���ɗ������ނƁA���ƂɎc���ꂽ���q�́A���������u���b�N�z�[�������яo���Ă������̂悤�Ɍ�����B�ʎq�I�Ȃ�炬����Η��q����������̂��������̂́A�v�����N���Ԃ̂悤�Ȓ��ɔ��ȊԂ����ɂ�������̂ɁA���ꂾ�ƌ����ɗ��q���a���������ƂɂȂ��Ă��܂��B���̂��܂����킹�邽�߂ɂ́A������Ɨ��\�ł͂��邪�A���݂̗��q���{���Ƀu���b�N�z�[�������яo���Ă����Ƃ���悢�B�����l���Ă��悢���Ƃ��z�[�L���O�͐��w�I�Ɏ������B
�@�������ău���b�N�z�[������͗��q�����o����A�u���b�N�z�[���͎��ʂ������Ă����B�z�[�L���O�����������ɂ��ƁA�u���b�N�z�[���̎��ʂƉ��x�Ƃ͔���Ⴗ��̂ŁA���ʂ������Ă����u���b�N�z�[���̉��x�͂���Ƒ��債�Ă����B�����Ă��܂��ɂ͂����������ɒB���đ唚���������N�����A�u���b�N�z�[���͏��ł��Ă��܂��B
�@�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ��N����͉̂F���̏����ɒa�������~�j�u���b�N�z�[��*�ɂ��Ă����ŁA�������k���Ăł���悤�ȑ傫�ȃu���b�N�z�[���ł́A�������鎿�ʂ��͂邩�ɏ���F���������z�����邩��A�u���b�N�z�[���͐������Â���Ƃ����B���Ȃ݂ɁA�~�j�u���b�N�z�[���̑��݂̉\�����w�E�����̂��z�[�L���O���B�ނ͂��Ƃ��ƃu���b�N�z�[���̌����҂ł���A�u���b�N�z�[���Ɋւ��邢�낢��ȐV����A�����Ă���g�~�X�^�[�E�u���b�N�z�[���h�Ȃ̂��B
* �z�[�L���O�ɂ��ƁA�F�������ɂ���ꂽ�u���b�N�z�[���̂����A���ʂ���Z���g���A���a����Z�����̈ꂃ���ȏ�̂��̂͌��݂��܂������c���Ă���\��������Ƃ����B
�P�V�D���Ђ����_�́A��ꐢ�I�̐V���������w���H
�@ ���A�f���q�_�ƉF���_�ł����Ƃ��z�b�g�Șb��Ƃ����Β��Ђ����_�ł��낤�B
�@ ���Ђ����_�̊�{�I�ȃA�C�f�A�́A�u���R�E�̂��ׂĂ̕����Ɨ͂̑���Ƃ͓_��̑f���q�ł͂Ȃ��g�Ђ��h����Ȃ�v�Ƃ������̂��B�f���q�̐��E�ł́A�V���q�̔�����\���ɂ���ė��q�̎�ނ͂ǂ�ǂ��Ă�������ł���B�����̐V���q�ɑ��Ă͈ꉞ�̐����͂�������̂́A�ʂ����ė��q�̎�ނɂ͍ی�������̂��Ƃ����^�₪�c��B����ɑ��A���Ђ����_�ł́A���̉F���ɂ͂������ނ̂Ђ������邾�����Ƃ����B
�@���Ђ����_�̌��^�́A�V�J�S��w�̓암�z��Y�ɂ���čl���o���ꂽ�B�z�q���`�����Ă���O�̃N�H�[�N�́A�Ђ��Ōł�����Ă���Ƃ�����_�ȉ������B����܂łƂ̓K�����ƈقȂ郆�j�[�N�ȗ��q�����Ă������̂Ђ������́A����܂ŕs���ł������������̂��Ƃ����܂������ł����̂Œ��ڂ𗁂т��̂����A�Ђ��͉��Ɠ������ԂŐU�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������A�����ɋꂵ�ނ悤�ȏ�ʂ��o�Ă��邱�Ƃ��킩�����B�܂��A�o�Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��֊��Ȃǂ��������āA���̂Ђ������͂������Y�ꋎ���Ă������B
�@�Ђ������ɑ����ēo�ꂵ���̂̓Q�[�W���_�ł���B���q�����т�����̂͂�͂藱�q�ł���Ƃ��A���q�̊Ԃɓ����͂̓Q�[�W���q�ƌĂ�闱�q�̌����ɂ���Đ�����Ƃ���B���̗��_�ɂ��������A�d�͂��Q�[�W���q�ɂ���Ē����Ă������͂��ł���B�Ƃ��낪�A���̗��_�ɉ����ďd�͂��L�q���悤�Ƃ���ƁA���_�̒��ɑ����̖�����ʂ��o�Ă��Ă��܂����Ƃ����������B���{�̒��i�U��Y��������ʂ��������邽�߂ɍl�Ă����u���肱�ݗ��_�v�������Ă��Ă���ɂ����Ȃ������B�d�͂�����߂ē���ȗ͂ł��邱�Ƃ͈ȑO����킩���Ă������A���̕ǂ̓Q�[�W���_�������Ă��Ă������Ȃ������킯�ł���B
�@�����ŁA�˔@�Ƃ��Č���ꂽ�̂����Ђ����_�������B�암�z��Y�̂Ђ��������������Ă����킸�����l�̌����҂̂����A�A�����J�̃W�����E�V�������c�ƃC�M���X�̃}�C�P���E�O���[���́A�암�z��Y�̂Ђ������ɁA���̌㔭�\���ꂽ�Ő�[�̗��_���Ƃ����A�Ђ��̒������v�����N�����i�P�O-33�����j�ɂ܂ŏk�߁A��Ԃ��㎟���Ƃ������Ђ����_���Ă����̂ł���B���Ђ��͈ꎟ���Ȃ̂ɁA��Ԃ͋㎟���Ƃ�����Ȑ��E�Ő��藧���̂������B
�@���Ђ��́A�㎟����Ԃł˂���A��]���A�X�s�����A�U�����A����Ɍ��������蕪��������Ƃ������悤�ɁA�l�Ԃ̐S�őz���\�Ȃ�����^�����ł���B�܂��A���Ђ��̐U���ɂ���āA���R�E�̎l�̗́A���Ȃ킿�d�́A�d���́A�ア�͂���ы����͂̂��ׂĂ�������B�e�X�̗͂̑���́A�U�����[�h�̈Ⴂ�Ő����ł���Ƃ����B�����Ē��Ђ��̉^���́A�v�����N�������������Ƒ傫�������������Ă݂�A�Q�[�W���_�ł����Ƃ���̃Q�[�W���q�̂ӂ�܂��Ƃ܂����������Ȃ��̂ƂȂ�B�܂�A�Q�[�W���q���o�����A�͂𒇉��`�ƂȂ�.�B
�@�������Ē��Ђ����_�́A�Q�[�W���_�ł͐�������ł������d�͂𒇉��Q�[�W���q�A���Ȃ킿�d�͎q�������̎O�̗͂ƂƂ��ɓ������_�Ŗ����Ȃ��L�q���Ă��܂����̂ł���B�܂��Ɏl�̗͂́g������h���B����́A�ߋ��̂����Ȃ�V�˂����Ȃ����Ȃ��������֎��Ȃ̂ł���B
�@���̒��Ђ����_�ɁA�암�z��Y�̃I���W�i���Ђ����_��Z���������w�e�����Ђ����_���o�����Ă���B�l�̗͂𒇉��Q�[�W���q�����łȂ��A�����̍\���ޗ��ƂȂ邷�ׂĂ̑f���q���A�ŏI�I�ɂ̓w�e�����Ђ��̐U���ɋA������Ƃ����B
�@���̃w�e�����Ђ��͗փS���̂悤�ɕ��Ă���A�����ƉE���ŐU������B�����ł͓�����̎��R�x�����U�����\�ŁA���̐U���ɂ��d�͎q�ȊO�̂��ׂĂ̗��q���o��������B�܂��A�E���ł͋㎟���̎��R�x�����U�����s�Ȃ��A���̐U���ɂ���ďd�͎q���o��������B�����ɂ����������̂����̈�Z�����́A�Ђ��̓����ɂ���Ƃ����B�O���猩���Ђ��͋㎟���ŐU�����A�����猩���Ђ��͈�Z�����ŐU������Ƃ����킯���B
�@���āA���Ђ����_�ł́A�F���͋㎟���̋�ԂƂ��Ēa�������Ƃ���B���̉F���ɂ͈ꎟ���̒��Ђ����������݂��A�͂͂܂����������Ɉ�ɓ��ꂳ��Ă����B���̉F���͎��ԂƂƂ��ɖc�����邪�A�v�����N�����̑傫���ɂ܂łȂ�P�O-44�b�i�v�����N���ԁj���o�߂����Ƃ��A���Ђ��͏d�͎q���o���������B�d�͂��܂����������킯�ł���B
�@���̌�A�㎟����Ԃ̂����̎O�����͂��̂܂ܖc�����Â������A�c��̘Z�����͖c�����邱�ƂȂ��A�v�����N�����̑傫���̂܂܂ł������B����̂��������܂��ȕ`���邽�߂ɁA�l�p�`���v���`���Ă݂悤�B���̎l�p�`�����ɎO�������Ă�����O������ԁA�c�ɘZ�������Ă����Z������ԂƂ���B�O������Ԃ̑傫���͏c�����̒����A�Z������Ԃ̑傫���͉������̒����ł���B�l�p�`�̓v�����N�����̑傫���Ƃ���B�܂蒴�~�N���Ȃ̂ŔF�m�̂��悤���Ȃ��B���̎l�p�`���c�̕����ɋϓ��Ƀr���[���ƐL�т��Ƃ���B�O������Ԃ��c������킯�ł���B�������̒����i�Z������Ԃ̑傫���j�͂��̂܂܂Ȃ̂ŁA�l�p�`�S�̂Ƃ��Č���ƒ����L�т�������{���邱�ƂɂȂ�B���̐��Ƃ����̂́A�F�m�͂ł��Ȃ�����ǂ��Z������Ԃ��Ƃ��Ȃ��Ă���E�E�E�B
�@�ǂ��ł��낤�A�����̓C���[�W�ł����ł��낤���B���Ђ��́A���������㎟����Ԃʼn^������̂ł���B�w�e�����Ђ��̏ꍇ�Ȃ�A�Ђ��̓��������킹�ē�������B
�@�a����������̉F���ł́A�d�͂������������Ƌ����͂��������A�����Ŏア�͂Ɠd���͂����������B���̃v���Z�X��S���Ē��Ђ��͂��܂��܂ȃQ�[�W���q���o�������A�܂��N�H�[�N��v�g���ȂǕ����̊�{�\���ޗ��ƂȂ�t�F���~���q���o���������B
�@���Ђ����_�́A����܂ł͓䂾�����f���q�������낢��Ȑ����A���Ƃ��A�ʎq�F�͊w*�ł����Ƃ���̃N�H�[�N�̐F�i�ԁE�E�j���ǂ����Č�����̂�����������Ƃ����B���~�N���ȘZ������Ԃɂ����钴�Ђ��̐U���̌����̂�����ŁA�N�H�[�N�̐F�����܂�炵���B
�@����Ȃ킯�ŁA���Ђ����_�́A���݂̑f���q�_�ʼnۑ�ƂȂ��Ă��邳�܂��܂ȓ����قƂ�lj������Ă��܂��炵���B�������A���Ђ����_�ň������w�́A�قƂ�ǒN�ɂ������Ȃ��悤�Ȓ�����ȑ㕨�ł���B�܂��A���������̗��_���\�����钴�Ђ��ɂ܂ŕ����ł���悤�ȗ��q������́A�Ƃ��Ă�����s�\�ł���B�܂�A���Ђ��̑��݂͎��ł������ɂȂ��B����ȂƂ��납��A���̗��_�ɑ��ẮA�u�P�Ȃ鐔�w�̗V�тł����āA�����ł͂Ȃ��v�Ƃ����ᔻ�̐����������Ă���B
�@��ꐢ�I�̐V���������w���A���������o�����Ă��܂����̂�������Ȃ��B
* �ʎq�F�͊w�Ƃ́A���R�E�̎l�̗͂̂����̋����͂���������ł���B�F�͊w�Ƃ����l�[�~���O������킩��悤�ɐF�̊T�O���Ƃ������Ă��邪�A�������{���ɐF�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̃A�C�f�A���암�z��Y���l���o�����������̂ł���B
�P�W�D��͂͂₪�āA�Ђ�����Ǝ���
�@�F���ɂ͐��牭�̋�͂�����Ƃ����B�X�̋�͂ɂ͈�Z�Z�Z���Ƃ���Z�Z�Z���Ƃ������鐯�X���܂܂�邩��A�C�̉����Ȃ�悤�Ȑ��̐������A����ł��F���S�̂���݂�A���[���b�p�嗤�Ƀn�`���O�C�Ƃ��������x�ł����Ȃ��B�F���͂قƂ�ǃJ���b�|�Ȃ̂��B
�@��͂ɂ́A���X�ƂƂ��ɃK�X��`������Ȃ鐯�ԃK�X�����݂��邪�A�����Y���͂̂悤�ɁA�K�X���قƂ�ǎ����Ă����͂�����B
�@��͂̑傫���͐������琔�\�����N���B�������̑��z�n��������u��͌n�v�́A��r�I�傫�����ނɑ������͂ł���B
�@��͂̓o���o���ɑ��݂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����琔����̏W�c���Ȃ��ĕ��z���Ă���B���\�܂ł̏����ȏW�c���u��͌Q�v�Ƃ����A���S���琔��̑傫�ȏW�c���u��͒c�v�Ƃ����B�܂��A��͒c�̕��z�ɂ����\�K�͂ŕЊ�肪�F�߂��Ă���A������u����͒c�v�ƌĂ�ł���B
�@���ꂼ��̑傫���́A��͌Q�����S�����N�A��͒c�����疜���N�A����͒c���������N���B�����Ă���ɁA�����̋�͏W�c���V���{���ʂ̖A�ɓ\������悤�ɘA�Ȃ��āA�l�����N���ƂɃt�F���X�̂悤�ɋK�����������ԉF���̑�K�͍\��������B
�@��͂̏W�c�������Ɍ`�����ꂽ���ɂ��ẮA�{�g���A�b�v���ƃg�b�v�_�E����������B�{�g���A�b�v���ł́A�F���ł͂܂������̋�͂����܂�A����炪�d�͂ŏW�܂��ċ�͌Q���͒c���`�����A����ɂ����̏W���̂Ƃ��Ē���͒c��F���̑�K�͍\�����ł����Ƃ���B�g�b�v�_�E�����ł͋t�ɁA�܂���K�͍\���ƂȂ鋐��ȃK�X�̉ł��A���ꂪ����͒c�̑f�ɂȂ��ɕ�����A���ꂪ����ɋ�͒c���͌Q�A�����ċ�͂ւƕ�����Ă������Ƃ���B
�@��͂̎�ނɂ́u�Q�����^�v�u�_��Q�����^�v�u�ȉ~�^�v�u�����Y�^�v�u�s�K���^�v�Ȃǂ�����B�ȉ~�^����Y�^�̋�͂͘V�N�̋�͂ŁA�V�����a�����鐯�͂قƂ�ǂȂ��B�s�K���^��͂́A���炩�̏Ռ����ĕό`������ꂽ�Ⴂ��͂��B�Q�����^�̋�͂͒��N�̋�͂Ƃ������Ƃ���ŁA�������̋�͌n�͉Q�����^�ł���B
�@��͂ǂ����͏Փ˂��邱�Ƃ����肦��B�Փ˂��ĕ����ꂽ���Ɗ�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂�����A
�����ꂸ�ɍ��̂��Ē��S�j������͂ƂȂ�A�c��Ȑ��̐�����Ȃ鑽���̐��c��a���������肷��B
�@���Ɠ��l�A��͂������͎����}����B��͂Ɋ܂܂�鐯�X�̑啔�������ł��āA���F��A�����q���A�u���b�N�z�[���ȂǂŐ�߂���悤�ɂȂ�A���ꂪ��͂̎����B���X�������A�g�̖т̂悾�悤�Ȍ��i�ł͂���B
�P�X�D�������̋�͌n�́A�����Ȃ��Ă���
�@��͌n�́A�p��� �f���������� �Ƃ� �l��������
�v���� �Ƃ��Ă��B�f���������� �Ƃ����̂̓~���N��\�킷�M���V�A�ꂩ�炫�Ă���̂ŁA�l��������
�v���� �ƂȂ����킯���B���{�ł́u�V�̐�v�ƌĂ��B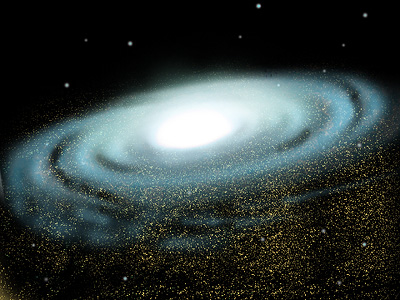
�@�ʏ�A�V�̐�Ƃ����Ɩ��ɉ��X�ƘA�Ȃ鐯�̒����т��w�����A���̓V�̐�̎p�Ƃ����͎̂��́A��͌n���قڐ^�����猩���p�Ȃ̂ł���B�Ƃ����Ă��A���z�n�͋�͌n�̒��S������Z�Z�Z���N���ւ��Ă��Ƃ���Ɉʒu����̂ŁA�������猩����͂̎p�ł���B
�@��͌n�̒��S�́A�V�̐�ł��ЂƂ��햾�邢�u���č��v�̕��p�ɂ���B�܂��A�V�̐�̂Ƃ���ǂ���ɂ͐^�����Ȍ��������Ă��邪�A�����͉����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ԕ��q�_�A������Í����_���Y���Ă���B�V���͂������琶�܂��B
�@��͌n�S�̂̌`��͉~�Ռ`�ŁA���S���̓A���p���`�ɖc���ł���Ƃ���邪�A�_�Ƃ�����������B
�@��͑S�̂́A��͒��S�̂܂����Q�����悤�ɉ�]���Ă���B�傫���͈�Z�����N���B���S���ɂ͔N�V�������������A�O���̉~�Օ����ɂ͔�r�I�Ⴂ�����W�܂��Ă���ƍl�����Ă���B
�@��͂̉�]�̗l�q�́A���S���Ɖ~�Օ��Ƃł͂����ԈقȂ�B���S���̉�]�͂Ђ���U��悤�Ȋ����ŁA���X�͂��̂Ђ��ɉ����Ĉ꒼���ɕ���ʼn�]����B�����̐��X�̉�]���鑬�x�́A���S����̋����ɔ�Ⴗ��B����A�~�Օ��̐��X�́A�����̍��͂�����̂̂��ׂĂ��قړ������x�ʼn��B���̂��߉~�Օ��ɂ����ẮA�O���̐������]����ԂɁA���a�����������Ȃ������̐��͂��̉^�s�����ɍ��킹�邽�߂ɓ��]���邱�ƂɂȂ�B
�@�~�Օ��ɂ͔g�������Ă���B���̔g�͐��̉^�s�Ƃ͊W�Ȃ��A���̃X�s�[�h�ʼnQ�������Ȃ���������Ƌ�͂��������B���X�́A���̔g�ɑ�������Ɖ^�s���x���������Ƃ��B���̂��߁A�����������ƂĂ����邭�Ȃ�B�Q�����^�ɖ��邭�Ȃ�킯�ŁA�Q�����^��͂̉Q�����̐��̂Ƃ͂���ł���B�������ۂɉQ�����^�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@��͒��S�̋����̈�ɂ́A���z���ʂ̓�܁Z���{���̎��ʂ��W�����Ă���B���̂��Ƃ͑O����\�z����Ă������Ƃ����A�h�C�c�̃}�b�N�X�E�v�����N�������̎l�N�ɂ킽��u��͒��S���̐��̒��ڊϑ��v�ɂ���ĉ��߂Ċm�F���ꂽ�B����܂ł́A��͒��S���̐��̎������x�ɂ��ԐړI�ɏd�͂����ς����Ă����̂ł���B���̋�͒��S���ɂ͐ԊO�����������炩�͂��邪�A�قƂ�ǂ̓_�[�N�}�^�[�Ő�߂��Ă���B�����炭�A�u���b�N�z�[���ł��낤�ƍl�����Ă���B
�@��͌n��������Ƃ��߂���͂́A�ꎵ�����N�̔ޕ��ɂ����}�[�����_�Ə��}�[�����_�ł���B�Ƃ��ɕs�K���^��͂��B���̗��}�[�����_�͎��͋�͌n�Ɨ��Â��ŁA��͌n�����͂Ƃ���O�d��͂��`�����Ă���B�}�[�����_�Ɏ����ŋ�͌n����߂���͂́A���}���`�b�N�Ȗ��O�Œm����A���h�����_��͂��B�����N�̔ޕ��ɂ���B��Z�����N�̑傫����L����Q�����^��͂ŁA��͌n�Ƃ悭�����\�������Ă���B���̋�͂��܂��A�O�d��͂̎��͂ƂȂ��Ă���B
���C���X�g�͂m�`�r�c�`�z�[���y�[�W�u�I�����C���X�y�[�X�m�[�g�v�ihttp://spaceboy.nasda.go.jp/Note/Note_j.html�j�����p
�Q�O�D���̋�͌n�ɂ́A�m�I�����̂̏Z�ސ����������邩�H
�@���̉F���ɂ́A���Ȃ����ς����Ă���Z�Z�Z���ȏ�̐����܂ދ�͂����牭����B���̉F���ɁA�u�n���̂悤�Ȑ�����������v�Ƃ����̂͂��肦�Ȃ��Ƃ���ق����A�����I�ɂ݂Ă����w�I�ɂ݂Ă��Ó����Ǝv����B�����A�����̈�����Ȃ��̂��Ƃ���A�_�̑��݂�M����������Ȃ��B
�@�����n���̂悤�Ȑ����ق��ɂ�����Ƃ���A�l�Ԃ̂悤�Ȓm�I�����̂��o�����Ă���ɈႢ�Ȃ��B���̉\����������ŕ\�킵����ǂ��Ȃ邩�Ƃ����̂ŁA�A�����J�̓V���w�҂ł���t�����N�E�h���C�N�́A�F�������������i�h���C�N�̎��j�Ȃ���̂��o�����B���͎��̂悤�ȕϐ�����Ȃ�B
�@�@��̗͂��j��ʂ��čP�����a�����镽�ϑ��x�i��N������̕��ϐ��j�@�A���̍P�����f���n�����m���@�B���̘f���n���Ő����̂����������鐯�̐��@�C���̐��Ŏ��ۂɐ����̂������E�i������m���@�D���̐����̂��m�I�����̂ɂ܂Ői������m���@�E���̐����̂����ِ̈������ɑ��R���^�N�g���Ƃ肤��قǂ̍��x�ȋZ�p�����B������m���@�F���̍��x�ȋZ�p�������ǂ�قǒ��Â����邩�̕��ώ���
�@���������ׂĂ������킹��悢�B�܂��A��N������ɒa������P���ɑ��āA���ِ̈������ƃR���^�N�g���Ƃ肤��قǂɍ��x�ȋZ�p�����B��������m�I�����̂����݂�����f���̑��݊m�����l���A���̂悤�ȕ������ǂ�قǒ����������邩�Ƃ������ϔN��������ɏ悶�Ă���B�܂�A��N������ɒa������ł��낤�u�����B�������鐯�v�̐��ɁA���̕����̕��ώ������悸�邱�Ƃɂ���āA��̗͂��j��ʂ��Ă��������������������������������邩�����߂Ă���킯�ł���B
�@�ł́A���ۂɎ��Z�����Ă݂悤�B�@�́A��͌n�̍P���̐�����͂̔N��Ŋ��������̂��B��͌n�̍P���̐��͈�܁Z�Z�����x�ƌ����Ă���A��͌n�̔N��F���̔N��i��܁Z���N�j�Ƃقړ������Ƃ���A���͈�Z�ƂȂ�B�A�́A�n���̂悤�Șf���͑��z�Ƃقړ������ʂ����P���łȂ��ƒa�����Ȃ��Ƃ�����������̂ŁA���̂悤�ȍP���̒a���m�����Z�E�Z�܂Ƃ��Ă݂�B����ɁA�f���n�����P���͘A��*1�ł͂Ȃ��P�Ɛ��ł���Ƃ��A�P�Ɛ������܂��m�����Z�E��ƌ��ς���B�����āA�����̊m�����悶�āZ�E�Z�Z�܂�B�B�́A���z�n�Ɠ��l�ƍl����ƈꂾ�B�C�́A�n���Ɠ��l�ƍl����ƈ�ɂȂ�B�D���A�n���Ɠ��l�ƍl����ƈ�ł���B�E�́A�m�I�����̂ɂ܂Ői�������̂Ȃ�A���̒��x�̋Z�p�͂��̂��Ɣ��B�������邾�낤����A�������Ƃ���B�F�́A�m�I�����̘̂f���ɓV�ϒn�ق��N����Ȃ�������A�Z�p�̌p���͖��i���s�Ȃ��邾�낤����A�܂���Z�Z�Z�N�Ƃ��Ă������B
�@���ʂ͌܁Z�Əo���B��͌n�����Ō܁Z�ł���B�S�F�����܂߂���A�ʂ����Ă����ɂȂ�̂��B
�@���̌܁Z�̐��Ƃ́A���炩�̌`�ŃR���^�N�g���Ƃ��\��������B��̃h���C�N���m���A����I�Y�}�v����w�����Ă�������݂�*2�B�������A�ڂڂ������ʂ͓����Ȃ������B���̌�����l�Ȏ��݂͂Ȃ��ꂽ���A�c��̔��Ȃǂ������č��͊J�X�x�ƂƂ�������Ԃł���B
*1 �݂��̈��͂Ɉ����ꍇ���āA���ʂ̏d�S�̂܂������]���镡���̐��̂��ƁB
*2 ���z�n�ɋ߂��A���z�n�ɂ悭�������X�ɓd�g�M���𑗂�A��J���ԁi����܁Z���ԁj�A���肩��̔�����҂����B
�Q�P�D�l�Ԍ����̉F���_�Ƃ͉�����H
�@�ꎵ���I�̃t�����X�̐��w�҂ł���N�w�҂ł�����f�J���g�́A�u���v���䂦�ɂ�ꂠ��v�Ƃ������B���́u���v���F���ɒu�������Ă݂悤�B�u�F���v���䂦�ɉF������v�ƂȂ�B
�@�F���ɉF���v�҂Ƃ������悤�Ȃ��̂�����A�F���͎v����������Ȃ��B�ł�����Ȃ��̂͂Ȃ��Ƃ���A�������߁u�F�����_�v�Ƃ��āu�_�v���䂦�ɉF������v�Ƃ������悤�Ȃ��ƂɂȂ낤�B�����A�_�͂��Ȃ��Ƃ��闧�ꂩ��͂ǂ��Ȃ�̂��B�u�v���v���Ƃ̂ł���c���ꂽ���݂́g�ЂƁh�������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����B���Ƃ���A�u�ЂƎv���䂦�ɉF������v�Ƃ����Ƃ���ւ��������B�ЂƂ̍ŏ��P�ʂ́u���v�ł���B����āA�ŏI�I�ɂ́u���v���䂦�ɉF������v�ƂȂ�B
�@�`���ł�����f�J���g�̊i���́u���v�ւ̒u���������A�F����_��ЂƈȊO�̂��̂ł���Ă݂���ǂ��Ȃ邩�B���Ƃ��A�L�����ƒu�������Ă݂�Ɓu�L�����v���䂦�ɃL��������v�ƂȂ�B�������L�����́A�������g�L�����h�ł��邱�Ƃ�m���Ă͂��Ȃ��B���ꂪ�L�����ł���Ƃ����̂́A�l�Ԃ����߂����Ƃł���B�܂�u�ЂƎv���䂦�ɃL��������v�Ȃ̂��B����͑Ώۂ��L�����łȂ��Ă������̂��ׂĂɂ��Ă͂܂�B�����āu�������F���v�ł���Ƃ���Ȃ�A���ǂ́u�ЂƎv���䂦�ɉF������v�Ƃ������ƂɋA������B
�@���̉F���ɂ́A�v�����N�萔�A�����A��{�d�ׁA�d�͒萔�ȂǁA���܂��܂ȕ����萔�����݂���B�����̕����萔�������A���̒l�����ق�̂킸���ł�����Ă����Ȃ�A���̉F���ɂ͐����͑��݂����A���������Đl�Ԃ����݂��Ă��Ȃ������낤�Ƃ����B����͂��������A���������Đl�Ԃ����݂����邪���Ƃ��A���̉F�������݂��Ă��邩�̂悤�ł���B
�@�܂������̒萔�́A�l�Ԃ������o�����@���◝�_�A�����Đl�Ԃ��s�Ȃ���������ϑ��Ɋ�Â��ē���ꂽ�l�Ȃ̂ł��邩��A�l�Ԃ��n�o�������̂��Ƃ�������B�����ċɘ_����Ȃ�A���̉F���́A�l�Ԃ��₪�ĂЂ˂���o���ł��낤�@���◝�_�����Ē萔�Ɏx�z����邪���Ƃ��ɏo���������̂悤�Ɍ�����B�ЂƎv�����䂦�ɖ@��������A���̖@���ɂ��������ĉF�������݂���Ƃ����킯�ł���B
�@�����Đ�ɂ��������悤�ɁA�F�����v���A�F�����邱�Ƃ̂ł��鑶�݂͐l�Ԃ����ł���B�F������Ȃ��F���͂����Ă��Ȃ��̂Ɠ������B���ǂ̂Ƃ���A���������̂́u�ЂƎv���䂦�ɉF������v�ł���B������u�l�Ԍ����̉F���v�Ƃ����B
�@���̒m�I�V�Y�ƍl����Ƃ悢�B
���R������
���E�ō����\�̖]�����u����v���n���C��

�@�����ȍ����V���䂪�傫�Ȃ��Ƃ�����Ă��ꂽ�i�������ŋ����g���Ă����j�B�W���l��Z�Z���A��C�̐��l�H�������Ȃ��n���C�̃}�E�i�P�A�R���ɁA���̃n�b�u���F���]�����������̂��\�͂�����^���˖]����������������B�勾���ꖇ�̋��ō\�������]�����Ƃ��Ă͐��E�ő�̌��a���E���ւ�B�A�����J�̗L���ȃp���}�R�V����̑�]�����ł���Z�Z�C���`�i�܂��j�ǂ܂肾����A�����ɑ傫�������킩�邾�낤�B���������Z�Z�������ꂽ�x�m�R���̖싅�̃{�[�����������邱�Ƃ��ł��A��Z�Z�����N�̔ޕ��������Ă��邩�����Ȍ����~�߂���Ƃ����B���H��͎l�Z�Z���~���B
�@�ߎ��O����������A�ԊO���܂ł̔g���i�Z�E�O�`�O�Z�}�C�N�����[�g���j�̌����Ƃ炦�ĉF���̉ʂċ߂��̋�͂��ϑ����A�F���J蓊��̃h���}��`�������B���ԕ����ɂ��������Č����Ȃ����n���̒a���̌���ɂ��A�ԊO�����Ƃ炦�邱�Ƃŗ�����邩������Ȃ��B���z�n�ȊO�̘f���n�̔��������҂���Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�n���C�̃}�E�i�P�A�R���Ƃ����̂́A���E�̓V�̊ϑ��̃��b�J�ƂȂ��Ă���B���{�̂���]�����̂ق��ɁA�n���C��w�̓�E���A�J�i�_�E�t�����X�E�n���C�̎O�E�Z�����A�J���t�H���j�A�H�ȑ�w�̈�Z���P�b�N�]�����A�m�`�r�`�̎O���ԊO���]�����A�C�M���X�̎O�E�����ԊO���]�����A���ݒ��̔����W�F�~�j�]�����ȂǁA�傫�Ȗ]�������Ђ��߂������Ă���A�ό������Ƃ��Ȃ��Ă���B�P�b�N�]�����̔��ˋ��͐��E�ő�ł��邪�A�\�荇�킹�̃��U�C�N�E�~���[�Ȃ̂ŁA���\�͂���̂ق�������B
�@����́A�����N�ꌎ�����A���̌������߂ĂƂ炦��t�@�[�X�g���C�g�ɐ������A�n�b�u���F���]�����ɗ��Ȃ������\���ؖ����Ă݂����B

�}�E�i�P�A�R���̓V����Q�i1997.7���݁j
|