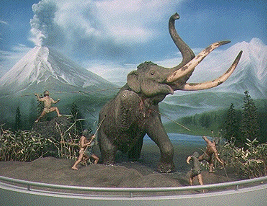|
第4章 地球の生き物(2)
11.突如として闇に包まれる人類の系統樹
12.私たちは、最初に花を愛したヒトを祖先にもちそこねた
13.人類進化の中心はシベリアだった?!
14.進化論の新潮流、細胞内共生説とは?
15.進化はウイルスによる伝染病だった?!
16.恐竜って超巨大なトカゲのこと?
17.恐竜は恒温〔温血)動物だったのか?
18.数え上げればきりがない恐竜の不思議
19.生物の大絶滅は二六〇〇万年周期?
20.動物園でマンモスに会える日
11.突如として闇に包まれる人類の系統樹
いよいよ、人類進化史上最大の謎にとりかかるとしよう。その謎とは、猿人→原人→旧人→新人の「→」に相当する部分は、いまだにミッシングリング(失われたつながり)のままであるということだ。つまり、そこには過渡的な特徴を示すヒトがいるはずなのだが、それに相当する化石はまだ見つかっていない*1。
ホモ・ハビリスは、猿人と原人をつなぐヒトと推定されてはいるが、しかし、このホモ・ハビリスが原人としての特徴をもっていたとするには、彼らが石器を使っていたことが証明されなければならない。いちおう、ハビリス型の石器とされているものは出てはいるが、猿人が使っていたという説もあり、結論はいまだに出ていない*2。
原人(ホモ・エレクトス)と旧人(ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)が有名)、そして旧人と新人(ホモ・サピエンス・サピエンス)の間はもっと深刻だ。そこにはホモ・ハビルスに相当するものすらない。進化の系統樹はここですっぽり闇に包まれる。時代が下っているのに、かえってわからなくなるなんて奇妙な話だ。
そこへ降ってわいたようにイブ仮説が登場する(本章の9参照)。研究者たちは大喜びでこの仮説に飛びついた。その結果、現生人類(新人)の進化の系統樹については多地域進化説とアフリカ起源説との2つが対立、ないしは折衷したものとなっている。
1.多地域進化説
一五〇万年前頃にアフリカからアジア、ヨーロッパへ進出していった原人が、旧人をへて新人に進化したとする(前述したように、これらのヒトどうしの間をつなぐ化石は発見されていない)。旧人としては一般的にはネアンデルタール人が有名だが(といってもネアンデルタール人は新人の直系祖先ではないというのが現在の定説)、ネアンデルタール人の化石は、ヨーロッパや中近東では見つかっているものの、アジアでは見つかっていない。このことから、アジアでは原人が中間型(まさにミッシングリンク)をへて直接新人へ移行したとする説もある。しかし、その中間型に相当する化石は出ていない。
2.アフリカ起源説
この説はイブ仮説にもとづく。二〇万年前頃に突如として北アフリカに現われた新人の子孫がヨーロッパとアジアへ進出し、先住の原人の子孫と入れ替わったとする。
3.折衷説
イブの子孫が広まったのはヨーロッパと中近東だけで、アジアは1のままであったとする。
どの説をとるにしても、最初の人類はアフリカにいたことだけは共通している。なお、原人や新人がアフリカを出て世界中に広まっていったことを「グレートジャーニー」と呼ぶ。
*1 新人へ進化したとされる旧人候補にホモ・ハイデルベルゲンシスという化石人類がいるが、これもあくまで仮説の域を出ていない。
*2 人類が作り出した最初の石器であろうとされているものにオルドヴァイ(オルドワン)型石器があり、これの製作者がホモ・ハビリスであろうといわれている。しかし、1996〜98年にかけてエチオピアのミドル・アワシュのブーリ村近くで発見された化石人類(猿人)、アウストラロピテクス・ガルヒ(ガルヒとは「驚き」と言うような意味)も石器を使っていたという説もあり、最初の石器の製作者が猿人なのか、ホモハビリスなのか結論はまだ出ていないようである。
12.私たちは、最初に花を愛したヒトを祖先にもちそこねた
猿人と原人をつなぐとされるホモ・ハビリスが登場したのは二〇〇万年前頃とされる。これは、もっとも新しい氷河時代が地球を訪れたときで*1、それは現在もつづいている。つまり私たちは氷河時代に生きているわけだ。氷河時代というのは、間に間氷期をおいて氷期が一〇万年(数万年とする説もある)くらいのサイクルで繰り返される。現在はちょうど間氷期にあたっている。
猿人の中から原人が現われたのは、この氷河時代のおかげかもしれない。氷期が訪れればいかに熱帯でも気温が下がり、これに適応できない動植物も現われる。猿人の世界も例外ではなく、とくに弱者に属するものたちにとっては、襲いかかる悪条件はより過酷なものとなったであろう。そして、これと必死に闘うことが進化をうながし、それが原人の誕生に結びついたのではなかろうか。よりたくましくなった原人の一部は、やがてアジアとヨーロッパに進出する。
問題はこのあとで、原人から旧人そして新人への進化の系統樹は、前項でも述べたようにかなりグチャグチャなのだ。
ところが一九九七年七月に、進化の系統樹に新たな光(混迷?)をもたらす研究成果が発表された。ミュンヘン大学とペンシルベニア大学の共同研究グループが、三万年前頃のネアンデルタール人化石からDNAを検出することに初めて成功したのである。このDNAと現代人およびサルのDNAを分析したところ、ネアンデルタール人は、遺伝子的に現代人とチンパンジーのほぼ中間に位置することが判明。また、現代人とネアンデルタール人の各祖先は、六〇万年前頃に共通の先祖から分化したことも分子時計法(本章の9参照)からわかった。
ネアンデルタール人は、二〇万年前頃に現われ、三万年前頃まで生存していたとされる*2。また、現代人の直系祖先である新人は、一〇万年前頃にアフリカから近東に進出し、五万年前頃にヨーロッパへと進出してクロマニヨン人になったという。もし、今回の研究報告が正しいとすると、これらのヒトの起源は六〇万年前頃にまでさかのぼることになる。この六〇万年前頃のヒトとはいったい何なのであろう。原人とのつながりは?
一方、イブ仮説によれば、現代人の祖先は二〇万年前頃のアフリカにいた女性であるという。現代人の進化の系統樹はかくのごとく、混乱しきっているのである。
いずれにしても、ネアンデルタール人はこれで、現代人の祖先ではないことが明らかとなった。「祖先」ではなく、「兄弟」だったのだ。
人類史上、最初に死者を埋葬し、花をもそなえた心やさしいネアンデルタール人。おそらく初めて火を起こす技法を習得したであろう優れた工人、ネアンデルタール人。ネアンデルタール人を祖先にもちそこねた私たちは、果たして幸せだったのか不幸だったのか。
*1 氷河時代は、先カンブリア紀の大昔からいくたびも地球を訪れている。
*2 1993年8月、日本・シリア合同調査隊が、シリアのデデリエ洞窟でネアンデルタール人の幼児のものと思われる約二〇〇点の骨を発掘した。約一〇万年前のものだという。写真はその復元像である。
13.人類進化の中心はシベリアだった?!
冬期にはマイナス四〇度以下となる厳寒の地、シベリアのレナ河のほとり、ディリング。一九八二年、ここから膨大な量の石器が出土した。
この石器群は驚くべきことに、アフリカのオルドバイ峡谷で発見された最古の石器(250万年前頃)よりも古いことが確認された。放射線年代測定によって、380万〜200万年前頃のものと判定されたのである。
いったいこれはどうしたことであろう? 初めて石器を使った原人は、アフリカに出現したのではなかったのか。ロシアの科学アカデミーの考古学者ユーリ・モチャノフは思いあぐねた末、石器の年代測定結果をそのまま素直に解釈する道を選んだ。「シベリアこそ人類進化の中心地、もしくはその一つである」と。
ユーリ・モチャノフが思い描いた新たなる人類進化の描像は、次のようなものだ。
二〇〇万年前に始まる氷河時代より以前は、地球全体は今よりも暖かかった。シベリアも現在ほどには寒くはなかったであろう(それでも十分に寒いが)。そんな頃のシベリアに石器を使う原人が現われた。やがて氷河時代が襲ってきて、原人たちは厳寒の世界にほうり込まれた*。この苛烈な自然環境の中を必死で生き抜く過程で、原人たちは新しい知恵と生活のシステムを獲得していった。そして、進化した原人たちはやがて世界へ広がっていった。
たしかに、これは一理ある話だ。そしてよく考えてみると、人類が熱帯地域で誕生したという正統派の説には、どこかひっかかるところがあるのも事実なのだ。シベリアにくらべれば天国のごときアフリカでのびのび暮らす類人猿が、何を好きこのんで直立二足歩行をし、さらに石器を使い、あげくには火を用いるほどに進化しなければならないのか。むしろ、シベリアにいた類人猿が寒さのために猿人や原人に進化し、やがて南下してアフリカへ来たとするほうが、つじつまが合うのではないか。ユーリ・モチャノフはこういっている。
「裸のルーシーがシベリアへ移り住む方向性はきわめて薄い」
ヒトと確定できる化石は、世界中をあわせてもたった三〇〇個程度だという。また、分子時計法にしても問題がないわけではない。ヒトの進化史はいまだ暗闇に包まれたままでいる。
* 氷河時代は熱帯のアフリカにも訪れたが、シベリアにくらべればとるに足らないものであったろう。
14.進化論の新潮流、細胞内共生説とは?
もっとも原始的な生命体は単細胞生物のバクテリアである。事実、地球に最初に現われた生命もバクテリアであった(本章の2参照)。以来、四〇億年近くを、他の動植物が幾度となく絶滅を繰り返すのをしりめに生き抜いているのだから、地球最強の生命とはバクテリアなのかもしれない。
ここで、二〇億年前頃のバクテリアの世界にワープしてみよう。これらのバクテリアの中には、光合成をしたり酸素呼吸を行なう好気性のものがいる一方で、酸素に対する抗体をもたない嫌気性のものもいた(今でもいる)。嫌気性バクテリアは、酸素のないところへ逃げ出すか、そのままのたれ死にするかの、いずれかを選ばねばならなかった。が、そのいずれをも選ばず、生き延びたものがいる。自身の生存を賭けて、好気性バクテリアを自分の体内にとり込み、自身の一部として手なづけたのである。これを細胞内共生という。
とり込まれたバクテリアのうち、光合成をするバクテリアは葉緑体となり、酸素呼吸を行なうバクテリアはミトコンドリアとなった。葉緑体もミトコンドリアも、細胞小器官と呼ばれる細胞内器官である。これにより、嫌気性バクテリアは好気性に変身するとともに、細胞それ自体がいっきに進化した。
これらの進化したバクテリアのうち、もっぱら葉緑体の機能を高めていったものは植物細胞に、また、ミトコンドリアの機能を高めていったものは動物細胞になった。動物細胞の葉緑体はしだいに退化し、やがて消失する。また動物細胞が運動能力を身につけたのは、自律運動を行なうバクテリアの亜種(スピロヘータの仲間)をとり込んで、それが細胞を動かす鞭毛になったものと思われる。
ここで重要なのは、葉緑体やミトコンドリアが形成されるプロセスにおいて、遺伝子を酸素からまもるべく、遺伝子をすっぽり包み込む核膜ができたことである。核膜とそれに包まれる遺伝子からなる器官を核というが、それまでは核をもたなかったバクテリアは、いまや核をもつ真核細胞へと進化したわけである。
細胞内共生を裏づける強力な発見も、一九六〇年代になされた。真核細胞の葉緑体やミトコンドリアが、核の遺伝子とは別個の独立したDNAをもつことが明らかにされたのである。
細胞内共生というのは実は、自然界では普通に見られる現象である。たとえば、マメ科の植物に見られる根粒には、その細胞の中にバクテリアがいる。このバクテリアは、マメから栄養をもらうかわりに、空気中の窒素をアンモニアなどに変え、マメが栄養として利用できるようにしている。また、アブラムシ(アリマキ)の体内の菌細胞にも多数のバクテリアが入り込み、共生体として生活している。
15.進化はウイルスによる伝染病だった?!
ウイルスとは簡単にいうと、自己増殖するための遺伝情報物質であるRNA、あるいはDNAと、それを保護するタンパク質のカプセルからなる半生命体(半物質?)である。自身では代謝が行なえないので、宿主の細胞に寄生してその宿主の代謝に依存しつつ、自身の増殖に必要な物質も、自分の遺伝情報にしたがって宿主につくってもらう。
これに対して、地球上の生物のほとんどは遺伝情報をDNAとしてもっている。RNAももってはいるが、RNAというのはDNA情報の仲介者のような役割を果たしている。たとえば、タンパク質をつくるDNA情報がRNAに転写されて、実際にはRNAが主役となってタンパク質を合成する。
ところが逆に、RNAのもつ遺伝情報をDNAに転写する逆転写酵素というものが、さまざまな生物の細胞内にあることがわかってきた。この酵素をもつRNAウイルスも存在する。レトロウイルスという。あのガンウイルスやエイズウイルスがそうである。
レトロウイルスは、自身のRNAがもつ遺伝情報を宿主の細胞のDNAに逆転写する。この情報は、宿主の細胞が増殖するたびにコピーされていく。そして場合によっては、世代を超えて子孫にまで遺伝することもある。もし、レトロウイルスのもつ遺伝情報が悪性のものではなく、たとえば首が長くなるといったようなものであったなら、このウイルスに感染した動物の首は長くなるかもしれない。そう、キリンになるのである。また、もし優れた脳の働きを発現させるものであったなら、このウイルスに感染したサルはヒトになるかもしれない。進化はウイルスによる伝染病だというわけである。
これまでに出土した化石の多くは、新しい種の出現(進化)は突然に起こったことを物語る。「進化はウイルスによる伝染病説」は、そのへんをわりあいにうまく説明できる。しかし弱点もある。それは、首が長くなるとか、頭がよくなるとかの大もとの遺伝情報は、いかなる経過をたどってウイルスにすり込まれたのかを説明できないことだ。
進化論はいまや、百花繚乱、百家争鳴の未開の分野と化しつつある。どうだろう、あなたも自分のオリジナル進化説を唱えてみては。
16.恐竜って超巨大なトカゲのこと?
恐竜というと、多くの人はイグアナのようなトカゲの超巨大なものをイメージするのがふつうだが、実際のところそれは間違いだ。
恐竜とは「直立歩行をする爬虫類」のことである。直立歩行というのは、トカゲやワニが、肘と膝を外に張り出してかろうじて体を浮かし、のたのたと這って歩くのとは異なり、哺乳類や鳥類と同様、脚をまっすぐに伸ばして歩くことである。体が大きいとか、顔が怖いとか、性質が獰猛だとかいうのは関係ない。ニワトリやイヌくらいの大きさの恐竜はいくらもいたし、中にはかわいらしい顔をした恐竜や、性質の温厚な恐竜だっていたかもしれない。“恐竜”という字面に惑わされないようにしよう。ちなみに、空を飛ぶ翼竜、ひれをもった水生の魚竜や首長竜などは恐竜に含まれない。系統的にも恐竜からはかけ離れた存在だ。
恐竜の祖先は、ペルム紀末の生物大絶滅(本章の6参照)を生き抜いた爬虫類の中から現われた。この生き物は、まだ半直立歩行の段階にあって、がに股でのそのそ歩いていたと思われる。一人前の恐竜が現われたのはおそらく二億三〇〇〇万年前頃だ。その化石はアルゼンチンで見つかっており、エオラプトルと命名されている。体長一mくらいの小型の恐竜で、短い前脚とよく発達した後脚をもっていた。
さて、恐竜の進化の系統樹はというと、人類以上に謎だらけである。まずわからないのは、直立歩行の能力を身につけた爬虫類(恐竜)の系統は一つだけにしぼられるのか、それとも、さまざまな系統の爬虫類が地球のあちこちで直立歩行の能力を獲得して恐竜になったのかということだ。恐竜の定義が「直立歩行をする爬虫類」という漠然としたものであるがゆえに、こういうことになってしまうのだろう。それと、人類の化石にくらべて恐竜の化石はごまんと見つかるために、かえっていろんなことがわかりすぎて混乱が生ずるということもあるだろう。
人類のアフリカ起源説にもみられるように、欧米の学界は単系統説を好む。それによると、恐竜の故郷は南米であるらしい。最古の恐竜化石がいくつも見つかっているからだ。しかし、それらが最古であるとする言いぶんには反対の声も多く、結局のところ真相は薮の中だ。
17.恐竜は恒温(温血)動物だったのか?
恒温動物である哺乳類や鳥類は直立歩行をしている。脳は高いところにあるから、そこへ血液を送り込むためには発達した心臓による強力な循環機能と、その機能を常時維持するだけのエネルギーがなければならない。このエネルギーを得るための燃焼状態が、恒温状態をもたらしているのである。一方、地面を這いつくばる爬虫類などは、そんなに大きなエネルギーは必要としない。体温が外気温に左右されてしまうほどのレベルの燃焼状態でも、らくに生きていけるのである。もっとも、長丁場を素早く動き回るスタミナはない。
前項でも述べたように、恐竜は哺乳類や鳥類と同様、直立歩行動物だ。直立歩行動物が生きていくためにはたくさんのエネルギーを必要とする。だとすると恐竜は恒温動物だったのではないか・・・。こうして、恐竜恒温動物説が浮上した。
またその一方では、大型の恐竜はその体のでかさゆえに体内で発生した熱が外へ逃げ出しにくいから、恐竜が恒温動物である必要はないという説も出されている。これを慣性恒温性説という。簡単にいうと、物体の体積が増える割合に比べて、その表面積が増える割合は小さい、という原理から導かれる説である。これによれば、体の大きいものほど体積に対する表面積の割合は小さく、小さいものほどその割合が大きいことになる。つまり、大型の恐竜ほど外皮から逃げ出す体温は少なくなるわけだ。と同時に、外気温の体内への影響も減少する。
たしかに、慣性恒温性は大型の恐竜にはつごうがよい。しかし、小型の恐竜には不利である。そこで、小型の肉食恐竜にかぎっては恒温動物化したという意見も少なからずある。小型の肉食恐竜は発達した後ろ脚と、体長の半分以上を占める丈夫な尻尾をもっており、時速数十kmで走ることも、獲物に襲いかかって蹴りをいれることもできただろうといわれる。そういう高いエネルギーレベルを維持するには、たいして機能しない慣性恒温性ではとうてい間に合わないというのがその言い分だ。
また、恒温動物化しないかわりに、小型の恐竜が体内の熱を逃がさないようにすべく、何らかの進化をしたとする説もある。そうした仮説の一つに、羽毛を生やした小型恐竜というのがある。この説を裏づける化石も、一九九六年に中国遼寧(リャオニン)省で発見されている。
18.数え上げればきりがない恐竜の不思議
不思議のデパート“恐竜”の、数ある謎のいくつかをご紹介しよう。
1.恐竜は「渡り」をした
恐竜は、冬場に南の暖かい土地で子供を育て、冬がすぎると子供とともに北へ移動したという。いわゆる「渡り」である。かなり長い距離を踏破したらしい。恐竜が歩くことはまた、その運動によって生ずる熱を体内に蓄えるためにも必要だった。変温性の大型恐竜は、体を高いエネルギーレベルに置いておかないと、非常時に素早い身のこなしができないのだ。
2.恐竜はラジエータを備えていた
ゴジラの背中に三角の背びれがいくつも生えているのを見て、不思議に思ったことはないだろうか。実はあの背びれ、ラジエータなのである。哺乳類のような発汗作用をもたない恐竜は、体内で生じた余分な熱を発散させるのが苦手だ。それでも非常に長い首や尻尾があれば、それらがラジエータの代わりになる。しかし、そういった特徴をもたない恐竜は、なるべく体積がとられずに表面積だけが増える工夫をしなければならなかった。それが、あの背びれという形になったわけだ。四つ脚の恐竜ではステゴザウルスなどが背びれをもっている。
また、これは恐竜ではないが、石炭紀後期からペルム紀前期にかけて繁栄した爬虫類の仲間に、背中に帆のあるものがいた。この帆は、太陽熱を効率よく吸収して体温を保つためと、体内の余分な熱を発散させるために用いられた。
3.恐竜は北極や南極にもいた
北極や南極から恐竜の化石が次々と見つかっている。この恐竜たちが生きていた頃の極地は現在よりも温暖だったが、それでも最低気温は零下に達した。そんな寒いところに彼らが定住していたのか、それとも、涼しいところを求めて渡りをした結果なのかまだわかっていない。
渡りであったとしても、冬場になれば彼らは南下したはずだ。暖かくて常緑樹の茂る土地までは、長いところで四六〇〇kmもあったという。一年でそれを往復するなんてちょっと信じられない。ならば、彼らは極地に定住していたのだろうか。だとすると、彼らは寒さに強い恒温動物だったのか。それとも羽毛を生やしたり、肉布団のような皮下脂肪を蓄えたりしたのだろうか? まったく、恐竜くんは謎だらけである。
19.生物の大絶滅は二六〇〇万年周期?
六五〇〇万年前の恐竜の絶滅は、きわめて劇的だ。その原因としては、内因説と外因説とがある。内因説には、「雌のホルモン異常」「便秘」「過剰適応(巨大になりすぎ)」「脳の縮小」「食中毒」「奇形児多発」「哺乳類による卵の乱獲」「種の寿命」などがある。
内因説は恐竜の絶滅だけを説明したものだが、実は絶滅したのは恐竜だけではなく、その他の生物も大量に滅んでいる。科の七〇%近くが死に絶えたといわれる。外因説ではその理由を、恐竜を含む生物系全体の生存が粉砕されてしまうような大異変として説明しているので、こちらのほうが信憑性が高いように思われる。
その外因説には、「もとは淡水湖であった北極海の氾濫」「長期かつ大規模な火山活動によるオゾン層破壊や温室効果」「太陽系に近い超新星の爆発」「太陽活動の激化」「月の大噴火」「パンゲアの分裂と移動にともなう気候変動」「地球磁場の逆転にともなう宇宙線シャワー」「酸素濃度の低下」などがある。
現在、もっとも受け入れられていると思われる説は次の2つだ。
1.巨大隕石衝突説
これについては本章の27でお話しているので、そちらを参照されたい。
2.周期説
生物の大絶滅は、二六〇〇万年の周期で繰り返されるというもの。その理由の一つとして、太陽系が銀河系を一周する(第3章の2参照)途上で巨大な分子雲に遭遇するというのがある。このとき、太陽系の外縁の彗星の巣(第3章の18参照)の安定が大きくかき乱されるために、多くの彗星が太陽に向かって落下し、そのうちのいくつかが地球に衝突して地球に大異変をもたらすという。
ある周期で繰り返されるのかどうかはさておいても、生物の大絶滅はこれまでに五回あったとされる(ビッグファイブ)。もっとも大規模なものはペルム紀末の大量絶滅だ(本章の6参照)。そして、もっとも劇的なのが恐竜の大絶滅である。
こうしてみると、すべての生物は、この世に出現して進化し、やがては滅び去るという宿命を背負わされているかのようである。地球にこれまで出現したすべての種のうち、九九%は絶滅しているという。人類とても、いつかは絶滅してしまうのだろうか。
20.動物園でマンモスに会える日
恐竜の化石の近くから発掘されたコハク。そのコハクに封じ込められていた一匹の蚊。ひょっとするとこの蚊は、恐竜の血を吸ったかもしれないと気づいた科学者は、その血をうまく分離できれば、恐竜ゲノム(恐竜の一個体を構成するのに必要な遺伝子セット)をそっくりそのまま抽出できる可能性があることに思いあたる。
これは、スピルバーグ監督の「ジュラシックパーク*」の筋書きを述べているのではない。筋書きのオリジナルを述べているのである。ジュラシックパークの原作者であるマイクル・クライトンは、これとまったく同じ経験をし、まったく同じことを考えた昆虫学者チャールズ・ペレグリーノから原作のネタを丸ごと得ているのだ。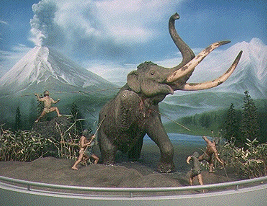
実際、こんなことが本当に可能なら恐竜の複製も夢ではなく、映画が現実になることもありうる。事実、シベリアで発見された氷詰めの赤ん坊マンモスの死体から、細胞を採取して培養を試みたところ、一度は分裂を始めたなどという、ウソかマコトかわからないような話も伝わっている。また、最新のバイオテクノロジーを用いた新たなマンモス人工受精計画も動き出しており、これには日本の鹿児島大学の研究チームも参加している。
では、現実に恐竜の遺伝子は抽出されているのだろうか。実情は何ともいえないというのが真相のようだ。一九九四年、米国ブリガムヤング大学の研究チームが、後期白亜紀の石炭層の中から出た恐竜の化石からDNAの抽出に成功したと発表したが、全面的な認知を得るまでにはいたっていない。また一九九五年には、中国の北京大学の研究チームが恐竜の卵の化石からDNAを抽出したと発表、ニュースはまたたく間に世界中を駆けめぐったが、これもどうやら問題が多すぎて、まともな成果とは受けとられていない。ロシアとか中国の研究発表というのは、その研究精度に関しては疑ってかかるのが常識となっているようである。
しかし、マンモスのDNAの抽出は、氷詰めの死体が出土しているくらいだからかなり見込みがある。そのDNAを使って生きたマンモスを作出するのも、クローン羊(第1章のコラム参照)がすでにつくられているのだから不可能ではない。代理母はもちろんゾウである。先述したように、このプロジェクトはすでに進行している。動物園で、生きたマンモスたちに会える日がいつかはやってくるだろう。
* ジュラシックとは、恐竜がもっとも繁栄した中生代ジュラ紀(二億一〇〇〇万〜一億四〇〇〇万年前頃)のことを指す。
※イラストは豊橋市自然史博物館ホームページ(http://www.tcp-net.ad.jp/tzb/tmnh/index.html)の「展示紹介」より引用
|